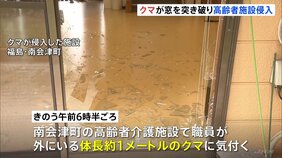お盆になると青森県の津軽や下北では、仏壇や盆棚に菓子を飾る独特の風習があります。この“カラフルなもなか”は、「お盆とうろう」と呼ばれています。食べることはできませんが、寒さの厳しい冬場に、この「お盆とうろう」づくりが鶴田町ではじまっています。
白川 舞 アナウンサー
「お盆の時期に飾られる『お盆とうろう』。2月の寒い時期に作業がピークを迎えています」
専用の金型で次々と焼き上げられていく“カラフルなもなか”。こちらが「お盆とうろう」です。
「お盆とうろう」は、野菜や果物などのお供え物のかわりに用いられる菓子で、津軽や下北では仏壇や盆棚に吊るす独特の風習が残っています。
彩りよく、そして賑やかに、先祖の霊をもてなすために派手な色遣いになっているとみられています。
県内では、お盆の時期にあわせてスーパーで多く販売されていました。鶴田町の「サトウ商事」は、「お盆とうろう」を焼くのには湿度がちょうどよくなる2月初旬から作業を始めていて、いま、ピークを迎えています。
コーンスターチともち米、そして着色料で彩り豊かに焼き上げていきます。
サトウ商事が「お盆とうろう」を作り始めたのは2019年から。それまで製造を担ってきた青森市の「山野辺商店」が54年の歴史に幕を閉じ、廃業したのがきっかけでした。
サトウ商事 伊藤武仁さん
「お盆とうろうは、県内で1軒・秋田で1軒。少なくなっていくなかで、古く伝わる伝統を心を込めて大事に作っています」
サトウ商事によりますと、「お盆とうろう」は3月末までに30万個以上を焼き上げたあと、袋詰めして出荷し、7月中旬ごろから県内のスーパーの店頭などに並ぶ予定です。