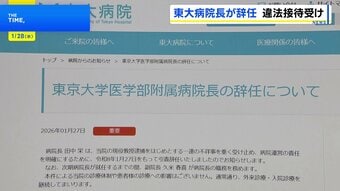13日、アルピニストの野口健さんが自身のSNSを更新し"避難所ガチャ"=「各避難所による生活環境格差」が存在することを指摘し、それを無くすために「日本版スフィア基準」を策定すべきと訴えました。

野口さんは「今回、よく『避難所ガチャ』という言葉を耳にします。確かに避難所によって生活環境にかなり差がある様に感じられました。」と率直に報告。「被災自治体の財政から生じる差というものもあれば、首長の避難所への熱量の差から生じるケースもあるのだろうと。」と、避難所の運営を被災自治体が負っている現状には限界があると指摘しました。
野口さんは過去の災害時に「ダンボールベッドを持って行った際に『日本人は布団の文化。ダンボールベッドなど必要ない』と。」などと自治体の首長に拒まれた経験を複数列記し、「災害が起こるたび、避難所の設営にあたふたする様子も見聞きします。」と、自治体による災害避難所の運営が決して万全ではないと綴っています。

そこで野口さんは「(紛争などにおける)避難所の国際基準」とも言える「スフィア基準」の適用を訴えています。「スフィア」とは1997年に複数の人道支援を行うNGOと赤十字・赤新月運動によって始められた、人道支援の質と説明責任の向上を目的とした取り組みです。
別の投稿で野口さんは、熊本地震の際に設営したテント村を専門家に「ここはスフィア基準に当てはめると80点ですよ。」と評価され「彼らが帰った後で慌ててスフィア基準を検索。一冊、取り寄せて勉強をしました。」と振り返りました。そして「ヒマラヤのベースキャンプに求められる生活環境とスフィア基準が目指すべき方向性が重なっている事に気がついた。」と、自らの経験に基づく創意工夫が災害支援につながっていたと述懐しています。

野口さんは「そこで避難所ガチャを作らないためにも『日本版スフィア基準』を作るべき。そして、各自治体が様々なアイテムを平時から用意をしておくこと。近くで災害が起これば、周辺の自治体が必要なアイテムを持って駆けつける。」「災害大国日本はそうやって助け合いながら、国難と立ち向かっていくべきだと。」と具体的なビジョンを披露。

「被災自治体による避難所の運営には限界がある。被災自治体の職員とて被災者。また、忙殺され疲弊していく。」と、被災自治体のみに避難所運営の責を負わせることの無理を指摘し、「『日本版スフィア基準』の策定は急務であると強く強く訴えていきたい。」と記しています。
【担当:芸能情報ステーション】