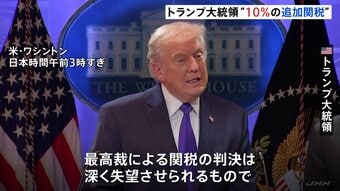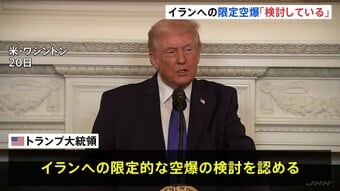ドラマ『さよならマエストロ~父と私のアパッシオナート~』。ここで描かれているのが地方オーケストラの姿だ。
オーケストラの中で、観客に背を向けて一心不乱に身体を動かしてオーケストラを操るのが「指揮者」。しかし、素人目には指揮者って本当に必要なの?と思うことはないだろうか。コンサートマスターがいれば指揮者はいなくても演奏できるのでは…。奏者は指揮棒を見ていない気がする、など。そこで今回、地方オーケストラで指揮棒を振るう天才指揮者役の西島秀俊さんの指揮レッスンを担当し、ドラマの制作発表でも指揮をした米津俊広氏(現:東京音楽大学講師)に、指揮者の仕事について素朴な疑問をぶつけてみた。

指揮者に必要なのは音楽的な引き出しと誠実さ
――オーケストラにおける指揮者の役割を教えてください。
たとえば、信号機のない交差点で、ドライバーや歩行者がルールを守れば事故は少ないでしょうが、やはり交通整理の方が立っていてくれたほうが安心できます。それと同じように、指揮者は奏者たちの前で合図を出しながら、安心して演奏できるように促すという大きな役割があります。また、それぞれ音楽に対する異なるイメージを持った音楽家が集まれば集まるほど、演奏の方向性がバラバラになりがちなので、指揮者にはオーケストラが目指す方向を示し、演奏をまとめあげる役割もあります。背を向けてはいますが、お客様からのパワーは背中で受けとめているつもりです。

――奏者たちは指揮をずっと見ながら演奏しているものなのでしょうか?
がっちりと目が合うということはあまりありませんが、指揮者と奏者は同じ時間・空間の中で、“イメージを共有しながら同じ音楽を奏でる”一体感を味わっています。奏者の皆さんは、指揮者の息遣いやオーラを感じ取って演奏しています。
――指揮者になるためにはどうすればよいのでしょうか?
指揮者は指揮者である前に“音楽家”でなければなりません。目の前にたくさんいる百戦錬磨の音楽家を導くためには、彼らと同等かそれ以上の“音楽の引き出し”を持っている必要があるからです。なので、まずは何か楽器を始めるところからでしょう。その後は音楽大学で指揮を専門的に学び、卒業後は海外へ留学したり、コンクールを受けて武者修行したり、人によってさまざまな道があります。

――本番に向けて、奏者と違って楽器の練習がないかわりに、具体的にどんな準備をされているのですか?
楽譜を読み、音楽のイメージや音響バランス、音色などを考えていきます。また、その作品を書いていた当時の作曲家の心理なども、楽譜や伝記を通して探ります。そのうえで、お客様にその作品をどう感じてもらいたいかを想像します。
以前、指揮をする筋肉を作ろうと自宅で鉄アレイを持ちながら練習したこともありました(笑)。ただ、奏者を前にしてこその指揮ですから、筋肉を作ったとしてもやはり実践で役に立たないと意味がありませんでした(苦笑)。経験を積んでいきながら、どうすれば効果的な指揮ができるのか、興味を持ち続けることが大切だと思います。
――リハーサルではどんなことをしていますか?
まずは実際に音を出して、奏者に指づかいや息づかいを確認してもらいながら、アンサンブルが難しいところを練習するというのはもちろんですが、オーケストラに名手が集まっていればいるほど、それぞれの奏者がすでに多くの“音楽的引き出し”を持っているので、自分の引き出しと照らし合わせ、コミュニケーションに多くの時間を割いています。
――指揮者によって演奏はどう変わるのでしょうか?
抽象的ですが、指揮者は奏者が音を出す前の心理をポジティブにする必要があります。指揮者が力んでしまうとうまくいかないですし、前向きな気持ちを引き出すやり方、奏者への思いやりのかけ方に個人差が出て、それが演奏に関わってくるものだと思っています。
――米津さんが考える「いい指揮者」とは?
“音楽とオーケストラに誠実である指揮者”と言えますでしょうか。音楽を通して信頼関係を築くことができること、奏者に自分の信念を共感させることができて、全員で共有できるよう導けることが、私の考えるいい指揮者の条件です。
学校で教わった音楽の授業だけではなかなか理解できない指揮者という職業。その仕事の奥深さと、彼らがオーケストラに与える影響の大きさ…『さよならマエストロ』で、この繊細な職人技の世界に触れてみては。
* * *
米津 俊広(よねづ としひろ)
1972年愛知県生まれ。愛知教育大学音楽科、同大学院を経て、東京音楽大学にて指揮を学ぶ。指揮を広上淳一、紙谷一衞各氏に師事。東京音楽大学在学中より指揮活動を開始。日本各地のオーケストラ、オペラ等の客演を重ね、2006年、スロヴェニア・フィルハーモニー管弦楽団音楽監督ジョージ・ペーリヴァニアン氏の推薦により同管弦楽団のアシスタントコンダクターとして渡欧、2010年まで研鑽を積んだ。
2008年9月、第28回マスタープレイヤーズ国際音楽コンクール(ヴェネツィア)の指揮部門にて、最高位並びにブルーノ・ワルター賞を受賞。 2009年10月、イタリア、トリエステで行われた、「第1回ヴィクトル・デ・サバタ国際指揮者コンクール」にてファイナリスト3名に選ばれた。
現在東京音楽大学指揮科講師。平成19年度、文化庁新進芸術家海外留学制度研修員。