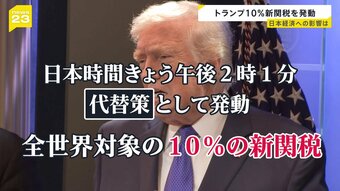MGCに出られず「身のほどを知った」
シーズン後半は良い流れを作ったが、23年シーズン前半の菊地は乗り切れなかった。世界陸上やアジア大会代表も狙って出場した2月の大阪マラソンは、2時間08分20秒で21位。最低限の目標ともいえた10月のMGC(マラソン・グランドチャンピオンシップ。パリ五輪代表3枠のうち2人が決定)出場権も得られず、4月のロッテルダムで再挑戦したが2時間21分09秒の47位に終わった。
「パリ五輪に出たいと言っていたのにMGCのスタートラインにも立てず、身のほどを知りました」
菊地がシーズン後半に向けて立て直すことができたのは、母校の城西大で初心に帰り、気持ちを前向きにできたからだった。「櫛部静二監督と話したり、学生と練習や生活を一緒にしたりして、自分で考えて自分で動くことの大切さを思い出しました。インターハイ(高校生の全国大会)に出たことのない自分は、大学時代、上に行きたいと思ったら頑張るしかなかったんです」。
中国電力の佐藤敦之監督は、予定外の不調に陥った後に何度も立て直したことを評価している。「7月のホクレンDistance Challengeはコロナで予定していた10000mに出られなかったのに、直後に出場した5000mを13分41秒で走りました。夏もアキレス腱を一度ケガしても、ちゃんと走れるようになった。12月の日本選手権10000m前も足首に違和感が出て、思い切り休んだのですが試合では力を発揮しました。そういう部分ができているので、マラソンの地力も上がっていると思います」。
地力が上がっている選手は、試合にそれほど合わせなくても好記録を出すケースがある。菊地自身も「試合なのでタイムは前後するとかもしれません」と、目標の61分30秒より速くなる可能性にも言及した。
淡々と走り切ることが東京マラソンにつながる
シーズン後半で立て直すことができた2つめの要因として、「一喜一憂しない」ことを挙げた。「佐藤監督と23年度の試合、練習をしていくなかで、一喜一憂しないで淡々とやっていこう、と話し合ったことを実践できています。人間、モチベーションが上がったり下がったりすることはありますが、それをコントロールできるようになって、外さないレースを続けることができています」。
全日本実業団ハーフマラソンでもそれを実行する。レースなので競り合う走りになるが、必要以上にテンションを上げてしまったら、出しきる走りになり、東京マラソンに悪影響が出てしまう。
「ニューイヤー駅伝後も良い練習ができています。タイムは(目安の61分30秒から)前後するかもしれませんが、どんな展開でも70~80%で淡々と走ります」
昨年は1月末の大阪ハーフマラソンを61分33秒(2位)で走り、2月末の大阪マラソンの中間点を63分21秒で通過した。今年は2月11日の今大会が61分30秒予定で、東京マラソンの中間点通過は62分台後半になると予想されている。
直前のハーフマラソンにプラス1分~1分半でマラソンの中間点を通過する。選手はある程度は計算するが、菊地は細かいこだわりを持たない。「東京マラソン中間点の62分台が速いとか、去年よりどうとか、比べて考えないで、中間点として淡々と通過できたらいいかな、と思っています」。
東京マラソンでその走りをするためにも、全日本実業団ハーフマラソンを淡々と走り切る。
(TEXT by 寺田辰朗 /フリーライター)