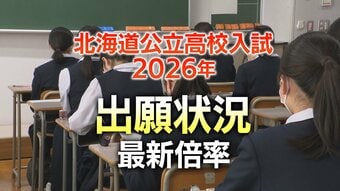“LGBT”パッケージの魔力
彼らのコメントにもにじみ出ていますが、近年「LGBT」「性的マイノリティ」といった言葉を目にする機会が増えてくる中、その語が一種のパッケージのように働くことでもたらされる弊害もあるのではないかと、あたし自身感じています。
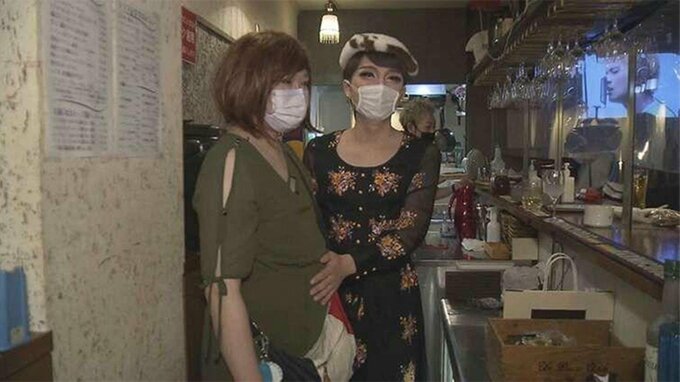
例えば性のあり方に関して、それぞれのセクシュアリティの持つ細やかな差異を覆い隠してしまうことで、そこに 「え?LGBTってこうなんじゃないの?」という新しい偏見が入り込む余地を許してしまったり。 「じゃあ実際どんな人間なのか」「どのような性を生きているのか」という、当事者のリアルに目を向ける機会をなくしてしまったり。
こういった問題は当事者間でも起きているように思いますし、読者のみなさんの中にも、日常を送っている中でそうした事例を目にしたことがあるかもしれません。
ましてや、この “LGBTパッケージ”の魔力がメディアに対して働くとなると、事は重大です。
報道というのは必然的にたくさんの人が目にするため、影響を受ける範囲はとても大きくなります。
どうしても紙面の幅やVTRの尺、わかりやすさのためにといった、取り上げる際の工夫や制限もあるでしょう。ですが、例えば「性的マイノリティ」の語を、その実情を捨象しあまりにシンプルに使ってしまったことで、報道側は可視化をうながそうという目的だったにも関わらず、それによって当事者が苦しむことになる事態も起こるかもしれません。「理解を広げようとして無理解が広がってしまった」という悲劇は自然と想定できるものであり、実は大変身近にあるリスクのひとつなのです。
ちかときみの事例、そして、ふたりが自分たちの経験について語ってくれた内容は、そうしたリスクの存在を改めて教えてくれるものでした。

当事者がメディアと接触するときに直面する問題は、今取り上げた“LGBTパッケージ”のみにとどまるものではありません。ほかの当事者たちから出てきた本音は、後編の記事でお伝えします。(“LGBT”再考 全2回 後編を読む)
満島てる子
オープンリーゲイの女装子。北海道大学文学研究科修了後、「7丁目のパウダールーム」の店長に。LGBTパレードを主催する「さっぽろレインボープライド」の実行委員を兼任。2021年7月よりWEBマガジン「Sitakke」で読者参加型のお悩み相談コラム【てる子のお悩み相談ルーム】を連載中。
編集:Sitakke編集部IKU