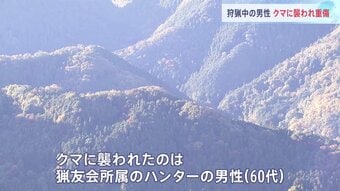MGCで新しい自分にチャレンジした2人
MGCの2人は新しい走り方に挑戦した。
一山は23kmでスパートしたことを次のように振り返った。
「あそこで出ない方がよかった、という意見も聞きますし、今までの私だったら“失敗したくない”という気持ちが働いて、思い切った走りはできなかったと思うんです。しかしMGCのときは、自分にチャレンジしたい自分がいました。一発勝負で、そこで決められなかったら後はない、ということもわかっていた。でもあの瞬間は、やってみたいという気持ちが強かったんです」
その一方で、フィニッシュした瞬間に、「これまでで一番嬉しい2番と思ったのは、本当の気持ち」だった。「しかし100%満足かといったら、あのときからそうじゃなかったですね」
レース中の判断は「よかった」、「悪かった」と白黒はっきり決められるものではない。しかし一山の中で、新しいことにチャレンジし、勝つことはできなかったが五輪代表権獲得に結びつけられた。
一山とは対照的だが、鈴木も新しいチャレンジをMGCで実行していた。終盤に一山と細田を追い上げ始めたところでは、“ケンカ走法”と言われた学生時代の駅伝の走りを解放した。だがそれまでは、集団の中で前に出なかった。「落ち着いた走り」で力を温存したのである。
単に走り方を変えたのでなく、そこにいたる判断力に研きがかかった。
「MGCを通して自分の頭がクリアになったことは、自分の成長だと思っています。冷静に走りながら、駅伝のときの大胆さを出すことができました。こうやって挑戦したら、このくらいができる。気持ちの持ち方をどうすべきか、わかってきましたね。自分の走りが明確になっきました」
2人とも新しい走りに、MGCという一発勝負の舞台でチャレンジした。その経験が、より複雑な状況になる駅伝でも力を発揮する可能性がある。
区間賞候補の廣中に対してどんな走りをするのか
MGCから1カ月半。今シーズンの競技会スケジュールは、マラソン選手にとって難しいものだ。
一山は「筋肉痛が取れるのに時間がかかりました」と言い、鈴木も「地味に疲労が残りました」と話した。万全に仕上げてくるのは正直、難しい状態だったと思われる。
2人が走る3区の区間賞候補筆頭は、世界陸上10000m7位の廣中である。
一山は1区区間賞など、クイーンズ駅伝では前半区間の区間上位の常連だった。鈴木も大学時代は3年時まで、全日本大学女子駅伝の区間賞を取り続けた。しかし世界レベルの廣中のスピードに、MGCを走った選手が対抗するのは難しい。
「タスキをもらった位置関係によって違ってくると思いますが、去年も廣中さんに抜かれた後も、チームの優勝のために落ち着いて走ることができました(廣中から12秒差で4区に中継した)。どういう展開になるかはわかりませんが、今年も全力を出し切る走りをしたいと思います」(一山)
「状況にもよると思いますが、仮に廣中さんと近い位置でタスキをもらったら、できる限り付いて行く気持ちで走ります。最後の方でもつれる形になったら、私も勝ち気で行きたいですね。ただ一番はチームの順位なので、自分のリズムを大事にして、自分らしい走りでチームに貢献したい」(鈴木)
廣中に対して善戦する、あるいは廣中を利用して自身の最大限のパフォーマンスを発揮する。MGCの経験を生かすことで、その走りを実行したい。
幸い2人ともMGC後に、痛みなどで走れない状態にはならなかった。短い休養期間を経てチームの駅伝に向けた練習に合流した。精神的に自身を奮い立たせられるのは、「優勝を目指すチームだからできている」(一山)という部分もあるだろう。
五輪マラソン代表選手への注目度は高い。だが、駅伝という競技は幅広い層の選手が参加する。42.195kmのマラソン選手も10000mが得意の選手も、さらには1500mなど中距離選手も出場する。選手の肩書きや知名度だけを見て駅伝を観戦するのはもったいない。その選手がどんな特徴を持ち、現在どんな状況に置かれているのか。選手のバックグラウンドを知ることで、駅伝観戦の面白さが倍増する。
(TEXT by 寺田辰朗 /フリーライター)
※写真は左から一山選手、鈴木選手