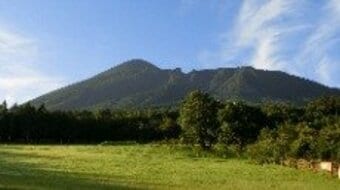野菜農家の安定した経営に向けた初めてのシンポジウムが24日、盛岡市で開かれました。厳しい環境が続く中、新たな技術を導入して奮闘する生産者の実践例が紹介されました。
このシンポジウムは、野菜の生産拡大につなげようと岩手県が初めて企画したもので、県内の農業関係者およそ120人が参加しました。
そして4人の生産者が、温度や湿度の他、光の量もコントロールできるハウスでの栽培などの先進事例を発表しました。
発表者の1人、盛岡市のキュウリ農家、澤口聡さんは去年、二酸化炭素発生装置を導入したことで、ハウスを増設することなく収穫量を上げた実績を紹介しました。澤口さんが導入した装置は、野菜が光合成を行うことでハウス内で不足する二酸化炭素を供給し、成育を促すものです。今年は暑さの影響で病害虫の発生もありましたが、収穫量は通常のハウス栽培よりおよそ3割増えたといいます。また二酸化炭素量をコントロールすることで同じ規格に育ちやすいため、分別作業の時間短縮にもつながったといいます。
(盛岡市のキュウリ農家 澤口聡さん)
「燃料代に加え装置も安いものではない。導入経費などを考えて良いなと思った人はぜひ挑戦してもらいたい」
生産資材の高騰や異常気象で農家を取り巻く環境は厳しさを増す中、24日は持続可能な経営をテーマに討論会も行われ、参加した人たちが野菜の生産拡大のヒントを探っていました。
注目の記事
北海道沖で17世紀以来の超巨大地震を起こす「ひずみ」すでに蓄積の恐れ 地震空白域に「すべり欠損」が溜め込むエネルギー 東北大学など研究チームが5年に及ぶ海底観測

白血病再発、抗がん剤が困難に…ダウン症の19歳・春斗さん「何のために生まれてきたのか」母が決断した命の危険ともなう選択

「手に入らないから自分で」ボンボンドロップシールなどの流行過熱で文具店は困惑 一方、手作り楽しむ子どもも

賠償金0円…小1女児殺害から25年の再々提訴「あの男の人生と反対だ」すべてを失った父の“終わらない闘い”【陳述全文】

港の岸壁の下から動物が呼吸するような音、確認すると…泳ぐ牛を発見 海保の潜水士が救助

「真矢って奴が、隣のクラスで授業中に…」SUGIZOが語った高校時代の“親友”との思い出 闘病中だった“親友”への思いが垣間見えた瞬間【LUNA SEA】