「水」を生かした地域づくりを進めている大町市で、小学生が水の大切さなどを学ぶ「水育(みずいく)」に取り組みました。
「水育」の教室の場となったのは、大町市にあるミネラルウォーターの工場。
12日は大町西小学校の4年生およそ30人が訪れ、豊かな森によって水が育まれることを学びました。
まずは手入れが行き届いた森の土と、日が当たらない森のやせた土とを見比べます。

そして、雨が降ったときの違いを模型で確かめました。
講師:
「A(豊かな森の土)は一番上の土で水が吸収され、蓄えられたけれど、B(やせた森の土)の土は水を吸収せずに泥水がそのまま流れてしまいました」
さらに、泥を含んだ水が土に浸み込み、地中の岩石などを通って濾過される様子も観察しました。
児童:
「すげー」
「透明じゃん」
「水」について学ぶ授業は市の教育委員会と市内にミネラルウォーターの工場を持つサントリーが協力し、今年度からすべての小学校で行うことにしています。
子どもたちは工場も見学し、降った雨がおよそ20年かけて地下水になることや、ミネラルウォーターとして流通するまでを学びました。
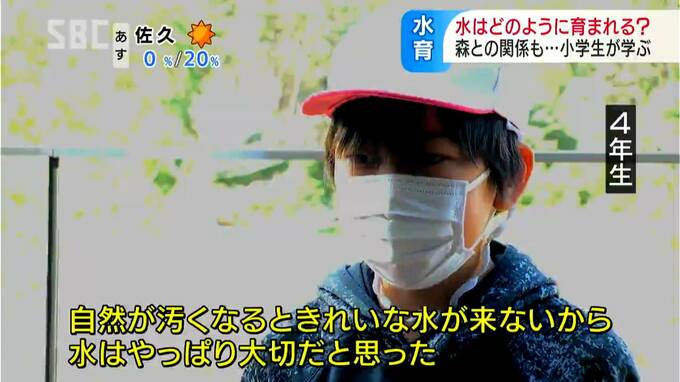
男子児童:
「自然が汚くなるときれいな水が来ないから水は大切だと思った」
女子児童:
「水をなるべく汚くさせないようにしたいと思いました」
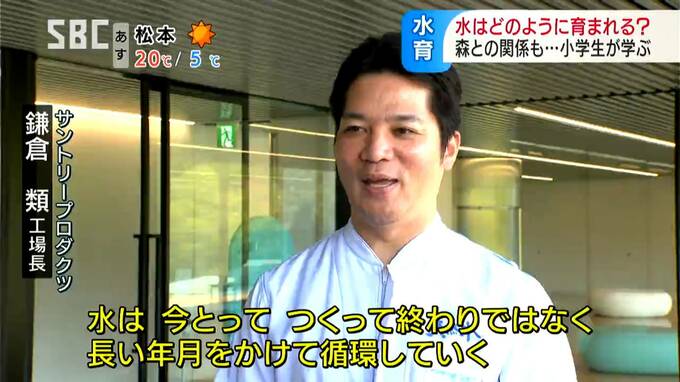
北アルプス信濃の森工場 鎌倉類工場長:
「水は今とってつくって終わりではなくて、長い年月をかけて循環していく」
「そんな仕組みがあってはじめておいしい水を大町のみんなが楽しめるし、大町の水を全国の人に届けられる。それを新たな気付きとして学んでもらいたい」

およそ2時間の授業の最後はお楽しみの試飲。
ふるさとの豊かな自然が水を育むことを学び、いっそうおいしく感じたようです。














