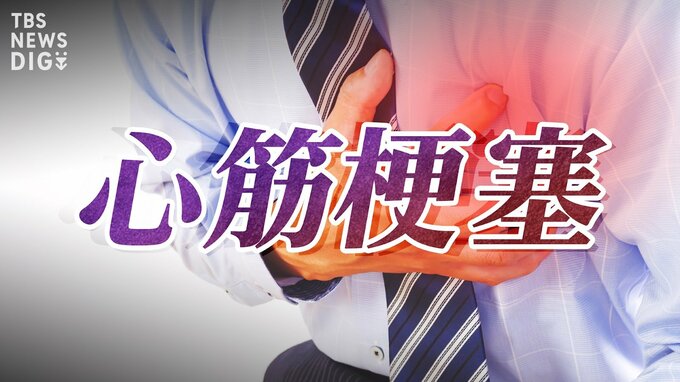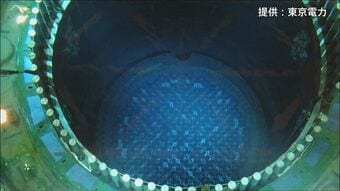寒い冬に多くなるという「心筋梗塞」。日本人の死因の第2位というこの病気はそもそもどんなものなのか。循環器内科医で国立循環器病研究センター副院長の野口輝夫さんに聞きました。
【心筋梗塞って、どんな病気?】

国立循環器病研究センター 野口輝夫 副院長
「心筋梗塞とは、心臓の血管が詰まって、心臓の筋肉(心筋)に栄養と酸素が十分に届かず、壊死を起こして元に戻らない状態です。今から40年ほど前、1980年ごろだと40%ほどの人が亡くなってしまう病気でした。今では病院で治療を受けられれば5%ほどまで死亡率は下がっています」

ーーではそれほど恐れなくてもいい病気になったということでしょうか?
「それは違います『病院で治療を受けたときの死亡率が5%』であって、処置を受けられずに家や出先で亡くなっている人は25%ほど、全体を合わせると未だに心筋梗塞で30%ほどの人が日本では亡くなっているとみられています。
さらに、命に別状はなくとも『一度壊死した心筋は元に戻らない』ことも恐ろしい点です。
心筋梗塞になって、なんとかカテーテル治療で、受け生き延びたとしても、心臓の力が弱くなり社会復帰できなかったり、家から出られなくなったりする人がいます。いわゆる「心不全」という状態です。
そうなってくると寿命はかなり短くなりますし、若い人であれば心臓移植の対象になってきます」