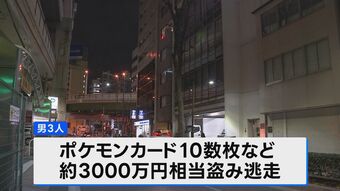習近平主席欠席の原因に?
インドのスリーラム・チャウリア教授(国際政治)は「中国は債務や経済戦争を利用して覇権を確立しようとしていて、そうした一方的なアプローチに不満を持っている国がインドを含めて多くある。米印は中国の影響力を押し返そうと連携を進めているが、今回のサミットでその動きはさらに収れんされた」と米印の連携強化を高く評価している。
また、インドの英字誌「オーガナイザー」のラヴィ・ミシュラ副編集長は「まさに経済回廊プロジェクトの発表こそが、習近平主席がここに来たくなかった理由でしょう。目の前で恥をかかされるわけですから」と話した。
チャウリア教授が指摘するように、アメリカは近年、中国やロシアへの対抗を念頭にインドとの関係強化を進めている。
長年「非同盟」を貫いてきたインドにも変化が見られ、アメリカとの関係は急速に深まっている。
長年構想に止まっていた日米豪印の枠組み「クアッド」が、急に動き出したのもその変化の現れであるが、チャンスと見たアメリカは、今年6月に国賓としてモディ首相をワシントンに招待し、安全保障分野を含む幅広い関係強化で合意した。
その延長にあるのが、今回のプロジェクトで、アメリカとしてはインドとの関係強化の具体策を打ち出しつつ、中国が関係強化に乗り出している中東諸国をつなぎとめるための装置としても使うことができる。

民主主義の弱点を乗り越えられるか…
ただ、懸念されるのはこのプロジェクトがどこまで現実のものとなるかだ。
ジョージ・ワシントン大学のオラパリー教授は「インドを拠点とする大規模な構想には、美辞麗句を並べただけで、実質的な成果はほとんど生み出さなかった歴史がある」と指摘。
「一帯一路構想の規模は他の追随を許さないし、インド政府もアメリカ政府も、中国政府のような一心不乱さは持ち合わせていない」と、参加各国のコミットメントがどこまで続くのかを不安視する。
来年はインドで総選挙が、アメリカでは大統領選挙が行われる。
政権交代があれば打ち出した構想が頓挫する懸念が出てくるだろう。それが中国のような国にはない、民主主義国家の弱点とも言える。
果たしてこのプロジェクトはどこまで現実のものになり、ゲームチェンジャーになりうるだろうか。
TBSワシントン支局長 樫元照幸(インド・デリーにて)