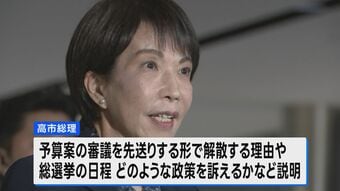■態度が変わった?ゼレンスキー、プーチン怒りの根源とは・・・

豊島:
ゼレンスキー大統領が2019年に就任した当時、停戦合意の履行には積極的だったんです。12月には、ミンスク合意の年内履行で4か国の首脳が合意するところまでいきました。ところが、親ロシア派の分離独立に反対するウクライナ民族派の反対があったり、(ゼレンスキーの)支持率が2割台にまで落ち込んでしまったんです。
ーー30%を切ったと。
豊島:
そうです。それを機にゼレンスキーさんの態度がどうも変わったという論評が多くてですね、ロシアに強い態度をとることで、自らの失地回復を訴えるように変わっていったんです。
そして2021年8月、ウクライナが46か国の首脳らを招き、クリミア奪還を目指す枠組み「クリミアプラットフォーム」を開催しました。これに対しロシアが批判を始めると2021年の10月、ウクライナは東部の親ロシア派との戦いにトルコ製のドローンで攻撃。これを機にロシアはウクライナ国境に大規模な軍を集めてしまいました。
ゼレンスキーさんの動きというのは、自分たちの主権国家の領土を守るとか、あるいはロシアに支配された自分たちの領土を取り戻すのだという動きで、これ自体は正しかったと思います。ただ、ロシアには間違ったメッセージを与えてしまったということになったんですね。
こうしたウクライナの動きに対し、ロシアはNATOにも、拡大しないですよね?と確認する条約を提示したところ、NATOからも「ゼロ回答」。ロシアは腹を決めてしまいました。
■ゼレンスキー大統領はウクライナを救えるか 責任を問う声も
豊島:
今もゼレンスキーさんは戦っていますが、戦いを止めれば、侵攻されてしまうわけですから、止められる状態にないですよね。ですので、武器の供与や国際社会の協力の呼びかけというのは正しいと思います。が、一方で国連機関が把握しているだけで既に4000人を超える人たちが亡くなってしまったのです。政治というのものが、国家国民を守ることを考えると、ゼレンスキ―さんの判断は、結果的に市民に多大な被害を出してしまうことにも繋がっています。
2014年以降、ロシアと話し合う枠組みを何とか持続できていれば、今回ほどの大規模な戦闘にまで至らなかったのかもしれません。しかし現在の状態に至ってしまい、ゼレンスキーさんの宰相としての責任を問う声さえ出ていますよね。
ーーもう始まった以上は全力で戦わなければいけない。止められない。世界中に協力を求めないといけない。ただ惜しむべくはこの8年間で真剣に話し合いなりして、こんな悲惨なことはなく終われなかったのかと?
豊島:
そうですね。最近ゼレンスキーさんは世界中にオンラインを繋ぎ、音楽祭やスポーツの場で自分たちの正当性を訴えていますが、本来政治とはかけ離れなくてはいけないような分野ですので、私にもゼレンスキーさんの言葉はとても響くんですけれども、その言葉を受ける側の我々は、この正当な発言の”正当性”はどこにあるのか。そこに注意し、冷静に受け止める必要があると思っています。