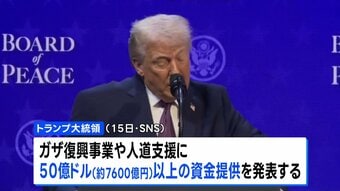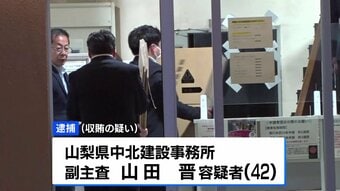■性別適合手術決意も…「自分たちの子どもが欲しい」
きみちゃんは中学で生徒会長を務め、スポーツも万能、活発な学生時代を過ごした。一方で幼い頃から、自分の性別が男であるのか女であるのか、迷い続けてきたという。
きみちゃん
「服を買う時もメンズの服を買ったり、女性らしい格好をしたら気持ちが変わるのかとか試したりもしましたけど…“女装している気持ち”になっていたというか…」
膨らむ胸に嫌悪感があり、さらしを巻いて目立たなくしていたことも。同じ悩みを抱える人たちと出会い、大学卒業後にトランスジェンダーであることを自覚した。
きみちゃん
「ノートにばーっと自分のことを書いて、父親と母親にカミングアウト的なことをした。男性としてこれからは生きていきたいっていうことと、それは親の育て方や親のせいじゃないってことを書いていました」
25歳で性同一性障害と診断され、性別適合手術を受けることを決めた。それは戸籍の性別を変えるためにも必要だった。
「性同一性障害特例法」いわゆる「特例法」では、戸籍の性別変更には、生殖腺(精巣・卵巣など)が無いこと、またはその機能を永遠に失っていることを条件としている。自分の子どもを持つことはできなくなるのだ。

きみちゃんは27歳のとき、乳腺を摘出した。胸には大きな手術の傷跡が残る。その後、子宮と卵巣も取る予定だった。しかし、パートナーのちかさんと出会い、考えを変えた。
きみちゃん
「子どもができる可能性があるならっていう話を何度かして、取ってしまったら(子どもを産む)可能性はゼロになるっていうところがあったので…」
ちかさん
「最後の決断は、本人に任せていた部分が大きかった。自分はどっちであれ付き合っていたというか、別にそれで変わることはなかったと思います」
自分たちの子どもが欲しい。きみちゃんは生殖機能を残す決断をした。戸籍は女性のまま、妻として婚姻届を提出。
きみちゃん
「女性の機能を使っているので女性だって言われたら、じゃあ女性なんじゃないって。みんなが思えばそれでいいんじゃない…男性だと思えば、男性だと思えば、別に自分は自分でしかないので」
2004年の特例法施行後、手術を受けて性別を変えた人は1万人を超える。医師は、手術はからだの性別に違和感を抱える人たちの生きやすさにつながると話す。
札幌医科大学 泌尿器科学講座 舛森直哉教授
「明らかに本人の生活の質が上がるのではないか。嫌悪感が軽減する。望む性別で社会でも活動できるようになると、社会的にも受容される」
しかし、手術でからだを変えないと戸籍の性別が変えられないとする特例法には、様々な意見がある。