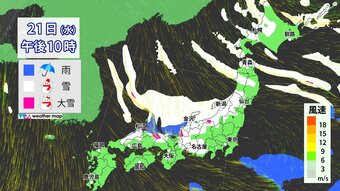病で声を失っても「自分の声」を取り戻せるアプリが名古屋大学で開発されている。「声」の尊さと向き合うがん患者と医師、アプリ開発者を1年間取材した。
「あなたの声がききたくて」無言の食卓で話しかけ続ける妻
愛知県春日井市に住む、田島浩幸さん(63)と妻の鈴子さん(63)。
(妻・鈴子さん)
「はい、うどんができました」
「味が薄かったかもしれない、何回か味見はしたけど熱いよ、ほら熱いって」
「かき揚げ入れたから冷めたかな」

夫婦2人の食卓。
手料理のうどんのことを夫に矢継ぎ早に話しかけるも、返答はない。
話すことが好きだった夫は、去年2月、ステージ4の咽頭がんで声帯を切除し「声」を失った。
(記者)
「Q田島さんはどんな声でしたか?」
(妻・鈴子さん)
「高校生の時から聞いているんだけど…優しい声だったと思いますよ。声を思い出すと、楽しかったですよね。楽しい声でした」

高校の同級生だった2人は38年前に結婚。昔から2人でしゃべる時間は特別だった。大型トラックの運転手として働いている田島さんは家から離れることも多く、電話をしてお互いの声を聞くことが日課だった。
でも、いまの田島さんの「声」は「電気喉頭」という機械の音だ。


電気喉頭とは、声帯がなく声を出せない人が言葉を発することを補助する機械。「ブー」という音を出す機械をのどに押し当てて使用する。
この音を口の中に反響させ、話していたときと同じように口を動かすと、言葉として聞くことができる。話すことは確かにできるが、「自分の声」とは全く違う、機械の音だ。
(田島さん)
「はっきり言って電気喉頭は、声っていうよりただの音だから…」
田島さんはこの音が与える印象が気になって、職場などではあまり使っていない。