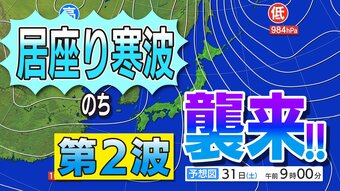6月26日は、国連の「国際麻薬乱用撲滅デー」だった。日本では6月20日から7月19日までの1か月間、キャンペーンとして『ダメ。ゼッタイ。』普及運動が実施されている。厚生労働省や都道府県などが、薬物乱用を禁止する啓蒙活動の一環だ。禁止薬物の売買、使用は当然ながら、日本だけの問題ではない。隣国・中国の麻薬事情について、東アジア情勢に詳しい、飯田和郎・元RKB解説委員長が、RKBラジオ『田畑竜介 Grooooow Up』で紹介した。
◆取り締まり強化の効果をアピール
国連の「国際麻薬乱用撲滅デー」に合わせ、中国の最高人民検察院(=日本の最高検察庁に相当)が記者会見を開いた。それによると、中国全土で禁止薬物に関する罪で検挙・逮捕された者は、2018年1月から今年5月までの5年5か月間で37万3,000人にのぼっている。
参考までに日本では、厚生労働省の最新の統計によると、2021年の1年間に薬物事件で摘発されたのは1万4,408人。このところ、横ばいが続く。
中国の人口は日本のおよそ10倍だから単純比較はできない。だが、最高人民検察院は「その数字は減っている。取り締まり強化の効果が現れてきた」と総括している。裏を返せば、かつては薬物がもっと社会に巣喰っていたといえる。
◆取引の巧妙化や低年齢化が目立つ
問題はここからだ。検察当局は、最近の薬物に関係する事犯の傾向をいくつか挙げて、警鐘を鳴らしている。
まず、タイプの異なる薬物が次々と出現している。例えば、合成薬物はその名前や種類は絶えず変わり、よりカモフラージュされやすくなっている。もちろん、当局も対策を取る。新しい合成薬物が流通しているのを発見した場合、すぐにリストアップする。だが、全体として薬物に関する犯罪事案のうち、新型の薬物が占める割合は急速に増加している。危険ドラッグと呼ばれる薬物もこの中に含まれる。
もう一つの傾向は、インターネットを使った禁止薬物の取引だ。密売人たちは一般に、電子決済のシステムを多用する。すなわち、「非接触方式」。「人、薬物、カネ」のプロセスを分離している。電子決済し、薬物を宅配するという方法が目立つという。捜査の手が及びにくく、巧妙化している。
さらに、傾向として麻酔薬、それに向精神薬を含んだ薬物に関する事案が増加している。当局の薬物取り締まりを強化するにつれ、麻薬グループの方は、従来型の麻薬の代替品として麻酔薬や向精神薬を密売するケースが目立ってきたという。
最後に、犯罪の低年齢化が著しい。未成年を含めた若い世代が、合成麻薬に手を染め、そして、犯罪を重ねる。つまり累犯が増えつつあるという。
いくつか紹介してきたが、とくに宅配方式で、薬物を受け渡す方法がもっとも厄介なようで、当局は中国の郵便、宅配業者に繰り返し、通知を出している。2022年、この宅配方式による麻薬の受け渡しに関連し、全国で3,000人以上を起訴したという。日本以上に電子マネー決済、ネットショッピングが浸透する中国だけに、という印象がある。