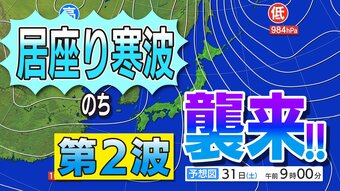◆少数民族にも「中華民族」という意識を高めたい
ここで本を紹介したい。タイトルは『満洲国 「民族協和」の実像』。本を書いたのは長野大学教授の塚瀬進さんだ。
“国民とは、ある歴史的状況下で、同じ国家への帰属意識を形成できた人々によって、構成されるものである。”
だが、中国の場合はちょっと違う。
“中華社会において国民という概念は存在せず、中華と夷狄(いてき=「異民族」のこと)の区分は、中華文明に教化されているかどうかにあり、民族などの範疇に基づいていなかった。
中国人とは、中国=中華という意識に支えられた地理的空間に居住する人、とでも解釈され、そこには同一性も一体感もなかった。現在の中華人民共和国は「中華民族」なる言葉を持ち出して、国民意識を高揚させようとしている。”
中国人とは民族の違いではなく、「中華という意識に支えられた地理的空間に居住する人」。だから、民族は異なっても、中国の地図の中に住む人は、中国人。そう意識させるものこそ「中華民族」というアイデンティティだ、ということだろう。
中華民族という意識を国民に高める。とりわけ、異なる文化を持つ少数民族が、同じ中華民族という意識を高める。そのために、教科書を換え、読み書きも標準中国語に統一したい――。習近平主席の思惑は、そういうことだろう。
逆に言うと、現状は「同じ中華民族」という意識が高まっていない、ということだ。国家が定めた統一教科書を使うよう、国は号令を出すが、少数民族が住む地域では依然、民族色の濃い教科書を用いるケースもあるという。
3年前のこと。内モンゴル自治区では、小学校や中学校の国語の授業を標準語で行う、モンゴル語の使用を制限する方針が示された。それに対し、保護者や教員らが抗議し、生徒が授業をボイコットした。市民によるデモに広がったほか、騒ぎは国境を越えた。隣国モンゴルの首都ウランバートルの中国大使館前で、同じ民族のモンゴル人が集まり、抗議集会を開いたほどだ。
◆圧力が強まるのは他の少数民族に対しても…
習近平主席は昨年7月、新疆ウイグル自治区を8年ぶりに訪問した。ここでも「中華民族の共同体意識を確固たるものにしょう」と指示した。
ちなみに、少数民族ウイグル族の人たちがふだん使うウイグル語も、日本語と文法的によく似ている。語順がほぼ同じだし、名詞の後に助詞が付く。モンゴル族同様、ウイグル族にとっても、日本語学習に入りやすいようだ。あの青い目、彫りの深い顔立ちのウイグル族で、見事な日本語を話す人が多い。
最後に気になることがひとつある。中国共産党中央の重要組織の一つに、統一戦線工作部という部門がある。統一戦線工作部は、民族問題、宗教問題などを扱う。ここのトップ、石泰峰部長は1年前まで、内モンゴル自治区の共産党組織のトップで、モンゴル族の子供たちに対し、標準中国語教育を進める責任者だった。
その石氏が、習近平主席から統一戦線工作部長へ抜てきされた。少数民族居住地域の教育現場に対する引き締めが、強まりそうだ。
◎飯田和郎(いいだ・かずお)
1960年生まれ。毎日新聞社で記者生活をスタートし佐賀、福岡両県での勤務を経て外信部へ。北京に計2回7年間、台北に3年間、特派員として駐在した。RKB毎日放送移籍後は報道局長、解説委員長などを歴任した。