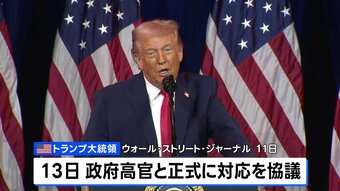■453万人の帰宅困難者 スマホへの懸念も
帰宅困難者については、10年前と比べ、テレワークの普及などの理由から1割程度減っていますが、それでも想定では、約453万人にのぼります。
一方で10年前と比べ、大幅に普及したスマートフォンへの懸念も。
想定では、アクセスの集中や電池切れによって、家族同士の安否確認が困難になるとされるほか、計画停電などで、長期に渡り思うような充電ができない可能性も指摘されています。
■高齢化進む地域 自助・共助・公助と、もう一つ大切なことは?
首都直下地震で最も被害が出ると想定されたのが、木造住宅が密集している地域です。

以前より住宅密集地域は減少傾向にあるものの、想定死者数の約4割にあたる2482人が火災によるものです。
一度火災が発生すれば、一気に広範囲に延焼。規模が大きくなれば、炎をまとった巨大なつむじ風=火災旋風が発生する懸念もあります。
例えば、東京・足立区には木造家屋が密集する地域があります。こうした地域は高齢化が進み、地震による火災などで被害が拡大する懸念があるということです。
足立区によると、消防団のなり手は減少。この地域では、小型の消火器を増やすなど、高齢者でもできる対策を進めています。

町内会長
「大災害では火が出る前にご近所で救出する、自助、共助、公助、あと“近所”っていうのがやっぱり一番大事かなと。常日頃から声かけとか大事にしたいと考えます」
■一人ひとりが自分のリスクを知っておくことが大切
いつか、必ず起こる首都直下地震。専門家は改めて、一人ひとりの備えの大切さを強調します。
東京都立大学・中林一樹名誉教授
「被害が減って“安全”側にはシフトしてますが、“安心”には程遠いです。一人ひとりが自分にとってのリスクが何かということを十分わきまえてもらうことが大事です」