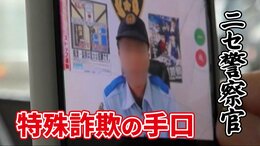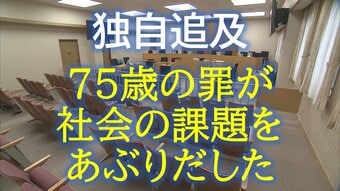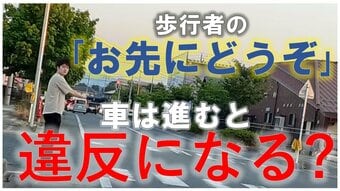長野県で起きた猟銃や刃物を持った男が男女4人を殺害した事件。
山形県内で猟銃を扱う人の思い、持つまでの仕組みを取材しました。
県猟友会・梅川信治会長「射撃場で弾が入っていなくても人に向けるとコラって言われる。そういう指導をしている」

県猟友会の梅川信治会長です。
今月25日、長野県中野市で青木政憲容疑者が警察官ら男女4人を殺害した事件。犯行には刃物と猟銃が使われ、青木容疑者は猟銃所持の許可を受けていたことがわかっています。

そもそも山形県内に猟銃を持つ人は何人いるのでしょうか。
県猟友会・梅川信治会長「だいたい1300人くらいが猟銃を持っている」
では、どうすれば銃を持てるのでしょうか。
県猟友会・梅川信治会長「精神鑑定は1番のこと、となり組やいろんな人の調査をちゃんとして許可する体制が決まっている」
銃を持つには警察の許可が必要。試験のほか、素行の調査も行われます。
許可を得たあとも、1年ごとに銃の状態を調査、3年ごとに許可の更新が必要で、毎回精神科の医師の診断書を提出するということです。(※狩猟にはこのほか県の狩猟免許を別に取得する)
厳重に管理されてまで、猟銃を持つ理由は。
県猟友会・梅川信治会長「今の若い人はジビエ(食材としての狩猟)や有害駆除を目的とした銃の所持だと思っている」
近年は人里でもイノシシやクマが目撃されています。
今年1月には、山形県南陽市の住宅街にイノシシが出没。3人が咬まれ、けがをしています。

県猟友会・梅川信治会長「(駆除をやめれば)畑が荒らされて農家がやめる方向になる。我々の仕事は重要な体制」
梅川会長は、猟銃を持つもの同士が互いにチェックし合えば、事件は防げたのではないかと考えています。
県猟友会・梅川信治会長「一匹狼にしてしまったというか(山形県は)年一回総会をしてみんなを集めているが、そういったコミュニケーションがなかったのかなと思っている」