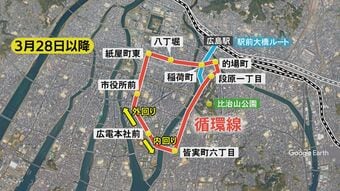モーリーさん
被爆者が少なくなると、最悪のシナリオではインターネット上でニセ情報が飛び交うことになるかもしれません。陰謀論とか、実は、原爆が落とされていなかったとか、原爆の被害がそれほど大きなものではなかったとか、何か政治的な意図で過剰に申告されていたとか、そういう誤った情報が広まる可能性があります。
なので、ニセ情報が飛び交うことが起きないように、被爆者の方々が語り継いできた言葉を届けること、情報・資料を保存して、情報を発信していくこと、そして世界中の人々が広島に訪れるハードルを下げていって、見ていただくことが大切です。G7の首脳が原爆資料館に行ったことで、かなりその重要性がより認識されたと思います。

青山高治 キャスター
漫画やアニメに夢中だったモーリー少年が大きくなって、国際ジャーナリストになったと。広島の街を取材していかがでしたか?
モーリーさん
今回は、何かが違うという感触があります。まだ、それが具体的に何なのかは、ゼレンスキー大統領が来て、あしたを終えてみないとわからないと思いますが、”広島の声” が世界に届く距離が短くなったように感じます。今の国際情勢、そして、ゼレンスキー大統領に注目が集まっていることなどが要因でしょう。今、広島で行われていること、そして、ここから発信される声が地球上の人々の心に深く届くことを期待しています。
河村キャスター
世界に声を届ける役割で言うと、国際メディアセンターでモーリーさんと一緒にいろんな国の記者のみなさんの考え方をうかがいました。

モーリー・ロバートソン さん
例えば、G7の中で経済制裁をするとなった場合、ドイツの人々が電気代の上昇を我慢する、日本だったら小麦の値段が上がるのを我慢するというような平和のために支払う対価が出てくるわけです。それと長期化したウクライナ侵略へのこの攻防戦でウクライナを支援し続けることに疲れが出てくるんですね。
これが何年にも及ぶと、疲れた有権者が次の選挙でより消極的な代表を選ぶ可能性もあります。こういうさまざまな複雑な問題が、民主主義であるからこそ、はらんでいるわけですね。
ですけれども、原点に立ち返ると、民主主義を守るためにウクライナで戦いが行われていて、そして、全ての国が民主的であれば、核兵器は二度と使用されない。つまり、ロシアや中国・イランのような体制も含めて民主主義をどう進めていくかについて、ここでじっくり考える必要があると思います。