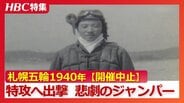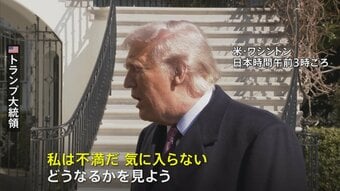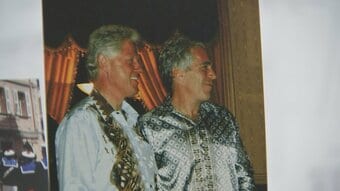国軍批判の活動を続けてきたミャンマー人男性が難民認定を求めた裁判で国側はこう主張した。
「原告がミャンマー政府からことさらに注目されるような事情はなく、迫害を受ける恐れがあるとは認められない」
全難連がまとめた「難民勝訴判決20選」には、裁判所が入管の判断を覆した20件の判決が収録されているが、入管側が難民不認定とした理由も示されている。
「反政府活動家として注視されるような存在であったとは認められません」
「政府が、ことさら警戒して迫害を企図するとは考えられません」
「特段、本国政府から関心を寄せられるようなものとは認められず」
「多数の中の1人としてデモ等に参加した程度に過ぎない」
「注視」「警戒」「関心」「把握」に「ことさら」「特段」を付けて難民性を否定するのは、入管側が用いてきた常とう句で、これこそが個別把握説によって難民該当性が判断されてきたことを示している。
20選の中の福岡地裁判決(10年3月)が重要な指摘をしている。
「仮に本国政府が極めて冷静で賢い政府であれば、最小限の労力で最大の萎縮効果が得られるように、迫害することが困難な著名な反政府団体の指導者等ではなく、その他大勢の活動家のうちの1人に過ぎない者を、ランダムに迫害するものと考えられる」
これは明らかに裁判所が入管側の個別把握説に疑問を呈したものだ。
今年3月、入管庁が公表した「難民該当性判断の手引」は、「迫害主体から個別的に認知(把握)されていると認められる場合、そのことは、本要件の該当性を判断する上で積極的な事情となり得るが、そのような事情が認められないことのみをもって、直ちに申請者が迫害を受けるおそれがないと判断されるものではない」という一文を明記した。これをどう見るか。
渡辺弁護士は「本来、難民の要件と判断は、裁量を許さないものだというのが難民条約の考えで、どの国に行っても同様の保護が受けられるようでなければならない。ところが、個別把握的な判断は、難民の受入れを自分たちの都合のいいように裁量的に調整するためのものでしかなかった。『手引』は結局のところ,この裁量的な要素を残していて、真に国際基準にのっとった難民行政を施行するという決意はみられない」と批判する。
その上で「法を改正し、3回目以上の難民申請者について送還を停止する規定を外すためには、適正な難民認定が行われているという前提が絶対に必要だ。『手引』はこれを意識して、個別把握説への批判をかわそうとしている」と見る。
「真に適正な基準に沿って今後の運用をするというのであれば、個別把握説にこだわり続けた過去を潔く認めた上で、国際水準に沿った判断に改めると明言すべきではないか。国会答弁は、事実に反しているし、不誠実としか言いようがない」