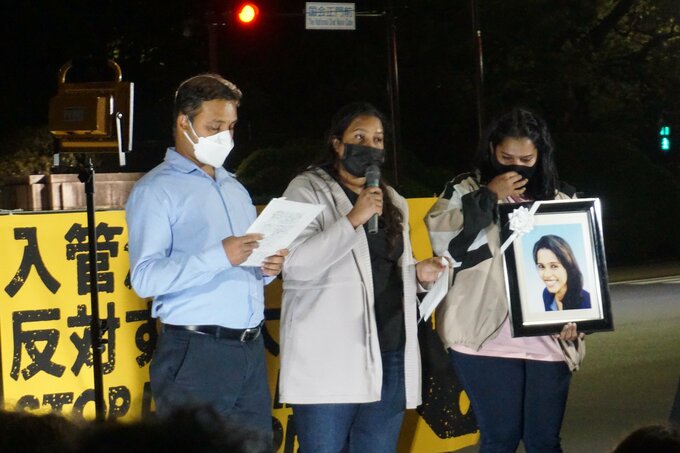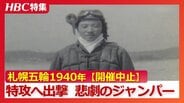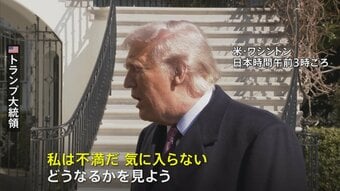人権上の問題が多いと国内外から批判されている入管法改正案が衆議院で可決され、参議院で審議入りしたが、これまでの国会審議での出入国在留管理庁(入管庁)の答弁や説明に疑問の声が上がっている。何が問われているのか。取材した。 (元TBSテレビ社会部長:神田和則)
<「難民をほとんど見つけることができません」(入管庁資料より)>
改正案の大きな柱の一つは、難民申請中は一律に送還できない現在の規定を変えて、3回以上の申請者を送還できるようにすることだ。その背景には、およそ難民には当たらない人が、送還逃れのために規定を誤用、乱用して申請を繰り返すから、入管施設に収容される人が増え、収容も長期化するという入管側の論法がある。
これを支える事実として、入管庁が繰り返し引用してきたのが、法務省の難民審査参与員でNPO法人「難民を助ける会」の名誉会長、柳瀬房子氏の国会発言だ。参与員とは、1次審査で難民認定されなかった申請者が不服を申し立てた場合、2次審査を担当する有識者で、柳瀬氏は05年の制度発足以来、その職にある。
柳瀬氏は2年前に廃案となった入管法改正案の国会審議に参考人として出席し、入管庁の主張に沿う発言をした。
「私自身、参与員が、入管として見落としている難民を探して認定したいと思っているのに、ほとんど見つけることができません」
「私だけでなくて、他の参与員の方、約100名ぐらいおられますが、難民と認定できたという申請者がほとんどいないのが現状です」
「難民の認定率が低いというのは、分母である申請者の中に難民がほとんどいないということを、みなさま、ぜひご理解下さい」(21年4月、衆議院法務委員会)
入管庁は、この発言が難民認定制度の乱用を裏付ける事実だとして、資料「現行入管法上の問題点」(21年12月)と「現行入管法の課題」(23年2月)に掲載した。しかし、柳瀬氏の発言を時系列で追うと、担当したという件数に疑問が浮かんできた。柳瀬氏は新聞のインタビューなどでもいろいろな数字を語っているので、一番手堅い部分を拾う。
今回の改正案の土台となったのは有識者会議の「提言」だが、この委員でもある柳瀬氏は、19年11月の第2回会合で次のように発言している。有識者会議が発足して間もない時期だったので出席者に与える印象は強かったと思う。
「私は約4000件の採決に関与、そのうち約1500件では直接審尋(注・対面審査)をし、あとの2500件程度は書面審査をした」
「私が直接審尋をした中で、難民認定されたのはこれまで4人、在留特別許可が認められた人が約22~23人いると思います。それが現実です」
これに対して21年4月の衆院法務委では、参考人として以下のように語った。
「担当した案件は2000件以上、2000人と3対1で対面で話している。一次審の難民調査官による結論を覆したい、難民と認定すべきと判断できたのは6件だけ。難民とは認められないものの人道上の配慮が必要と考え、在留特別許可を出すべきと意見を出したのは12件ある」
「私どもの参与員の審査は、あらためて第三者として、申請者の意見を聞き、徹底的に聞き直す。しかし実際には、入管が認定しなかった申請者の中から、新たに難民だと思える人はほとんど出会えないのが実態」
在留特別許可件数が、後になってほぼ半減していることも不思議だが、注目したいのは、発言によれば、19年11月から21年4月までの1年半で約500件もの対面審査をしたという点だ。また別の“物差し”で見ても、05年から19年までの15年間で対面審査が約1500件、1年あたりにして100件前後、書面審査も含めると260件以上担当したことになる。
ちなみに19年の1年間を見ると参与員全体で、対面審査は582件、20年は513件と入管庁は答弁している。1年半で500件がいかに多いかがわかると思う。私が取材した元参与員は「あり得ない」と断言した。