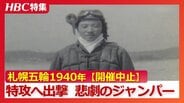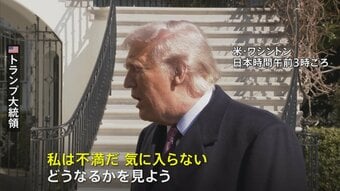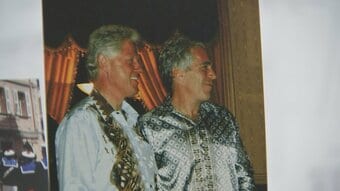柳瀬発言を受けて全国難民弁護団連絡会議(全難連)は、日本弁護士連合会推薦の元参与員に対して緊急アンケートを実施した。その結果、常設された班に所属した10人の年間の平均担当件数は36.3件だった。3人1組の常設班は、普通は月2回招集されるので、毎回、対面審査が2件実施されるとして「年間50件程度が上限」とも指摘した。

そうなると、柳瀬氏の担当は、なぜ異常に多いのか。
記録を精査するまでもなく短時間で不認定と判断できるような案件ばかりが集中しているのであれば、「難民はほとんど見つけられない」のは当然だろう。だが、それは柳瀬氏に限定されたことで、参与員全体を代表して語る材料にはならない。さらに「申請者の意見を聞き、徹底的に聞き直す」(柳瀬氏)こととは矛盾する。
一方で、数字を間違えたのであれば、難民申請者の運命を左右しかねない法案で、大事な参考人を務める資質が問われ、発言の信用性が揺らぐ。
そもそも参与員は組織体ではない。長く担当しているからと言って、すべての参与員を背負って発言すること自体があり得ないし、入管庁が他の参与員の意見を無視している理由もわからない。
全難連のアンケート調査にあたった高橋済弁護士は「移民政策の話は印象に操作されやすい。だから事実をベースに議論をしなければならない。柳瀬氏は、難民と認められるはずの人が送還されて、人の命を奪うかもしれない法案の審議で『難民はほとんどいない』と重要な発言をした。そのことの真偽は、まさに法改正が本当に必要なのかどうかの根幹に関わる」と指摘する。あいまいにしてはならない。
<「両親の帰国を条件に子どもに在留特別許可をするような運用はしていない」(入管庁国会答弁)>
家族を引き離さないで!非正規滞在の当事者や支援者が訴える会見が、5月15日に開かれた。 まず、衆議院法務委(4月28日)でのやりとりから引用する。
▽本村伸子議員(共産)
「両親に在留資格がない子どもの中には、両親が帰国すれば子どもに在留資格を与えるという教示を受けた家族もいるというふうに聞いていますけれども、これは事実でしょうか」
▽西山卓爾・入管庁次長
「入管庁では、ご指摘のような両親が帰国することを条件に、子どもに在留特別許可をするような運用は行っておりません」
会見ではこの発言に対し、NPO法人「移住者と連帯する全国ネットワーク共同代表理事」の鈴木江理子・国士舘大教授が「子どもの在留特別許可と引き換えに、親の帰国を迫ることはしていないという答弁はうそ」と強く反論、「入管職員は親に対して『お父さん、お母さんが帰ると言わない限り、子どもは苦しむよ』と言ってきた」と自ら体験した事実を明らかにした。
会見では、非正規滞在の家族の厳しい状況が次々と語られた。
一時的に収容を解かれる「仮放免」の家族を支援してきたビスカルド篤子さんは、子どもたちが泣き叫ぶ中で、入管職員が父親を収容し送還した場面を目の前で見てきたと語り、「一家の大黒柱を失うと、家族にとっては兵糧攻めになってしまう。お母さんはどんなに気丈に振る舞っていても2年、3年がたつと心が折れて追い詰められていく」、そして「自分の身代わりに親が強制送還されたとしたら、子どもたちはどれほど自分を責めることになるでしょうか」と問い掛けた。
両親がペルー出身の大学生の女性は、中学3年の時に父親が強制送還され、母親、弟と暮らしてきた。「私は日本で生まれて、日本で育った。『荷物をまとめて帰りなさい』というのは、知らない国に行けと言われているのと同じ」と苦しい胸の内を明かした。現在は「仮放免」なので住民票がなく、就労も認められない。「一生に一度の晴れ舞台の成人式の招待状も届かず、当日は家に閉じこもったまま過ごした。就活も極めて難しい。私たちの故郷は間違いなく日本。ただ親とここで暮らしたい、静かに平凡な日常を送りたいだけ」と訴えた。
元中学教諭で、両親が強制退去となった姉妹の未成年後見人を務めた大谷千晴さんは「日本で生まれ育って、教育を受けた子どもたちは、日本の財産。子を産み育て、働いて税金を納め、この社会の一員として生きていく子どもたちを大切にしてほしい」と呼び掛けた。

難民審査参与員も務める鈴木教授は、「人間としての権利は在留資格に先行する。成長過程にいる子どもには一刻の猶予もない。入管法改定の審議よりも、子どもの最善の利益を考えて、まず現行制度の下で在留特別許可か、難民認定による正規化が先だ」と強調した。
耳を澄ませて、当事者の声を聞かなければならない。
<「難民かどうかの判断に“個別把握説”は採用していない」(入管庁国会答弁)>
日本の難民認定数が欧米諸国に比べて極端に低いことは再三指摘されてきたが、その原因は、迫害や迫害の恐れを国際基準より狭く解釈してきたことにある。全難連代表の渡辺彰悟弁護士は「これまで入管側は、迫害する側から個別に把握されていなければ難民とは認定しない独自の基準、個別把握説をとってきた。国際的な判断基準とは異なっていた」と指摘する。
ところが入管庁は、国会答弁で個別把握説を否定した。参議院法務委員会(5月16日)でのやりとりを引用する。
▽谷合正明議員(公明)
「個別把握論は採用されているのかどうか、うかがいたい」
▽西山卓爾・入管庁次長
「わが国では、そもそも迫害を受けるおそれの要件の該当性判断にあたって、ご指摘のような考え方(注・個別把握説)は採用していない」
だが、これはまったく違う。私の過去の取材でも明らかだ。