持続可能な社会への取り組みを紹介するSDGsプロジェクト「地球を笑顔にするWEEK」。
今回は、大昔から時代を超えて行われている「物々交換」です。
交換するのは、紙とパン、なぜ成立しているのでしょうか?
物々交換を行っているのは、松本市北深志の「そればな」。
信州大学近くの住宅街にあり、小麦粉を使わず米粉で作ったグルテンフリーの菓子やパンを販売しています。
■尾関アナウンサー
「このお店の物々交換は何を交換している?」
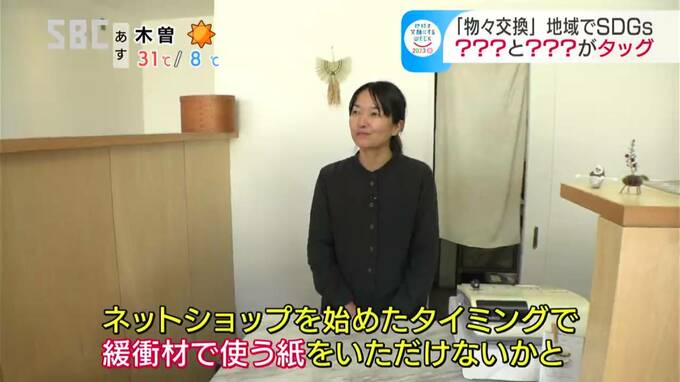
■三宅利佳さん
「もともと交流のあった藤原印刷さんにお願いをしてネットショップを始めたタイミングで緩衝材で使う紙をいただけないかと」 「期限切れが近い商品を引き取っていただいてその代わりに紙をいただくということをお願いして始めました」

店から渡しているのは、賞味期限切れが近いパンや菓子。
印刷会社からはどんな紙をもらっているのでしょうか。
■三宅利佳さん
「こんな感じで適当な大きさに切っていただいていて」
■尾関アナウンサー
「緩衝材と聞いていたので細かくなっているのかなと思ったのですが画用紙のような状態なんですね」
もらうのは、会社で使わなくなった製本用の紙です。

この店では、通販で商品を送るときの緩衝材のほか、商品に添えるメッセージカードとして使っています。
「物々交換」を始めたきっかけが、「もったいない」という気持ちからでした。
■三宅利佳さん
「お客さんのもとに届いてもきっと捨ててしまうものを買いたくないなという思いもあって(藤原印刷に)相談したんです」
一方、藤原印刷では…
■尾関アナウンサー
「そればなのパンや焼き菓子はどのように利用している?」
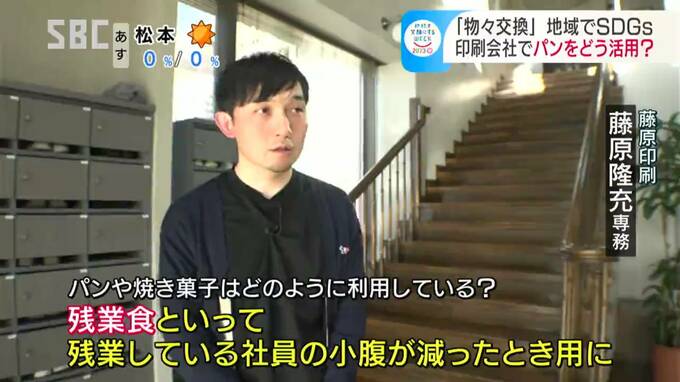
■藤原印刷藤原隆充(ふじわら・たかみち)専務取締役
「残業食と言って残業している社員の小腹が減った時用に菓子パンやお菓子を出すという仕組みをずっと前からやっていてそればなさんのお菓子があるときは特別なものとして提供している」
その「残業食」を見せてもらうと…。
■尾関アナウンサー
「あった!」
■藤原専務
「ここにこうした形で軽食総菜パンや菓子パンを多種様々用意している」
印刷業は、発注を受けて仕事をすることから、この会社も業務量に波があって残業が発生することが多く、伝統的にこうした「残業食」を社員に提供してきたということです。
ただ、その残業食と交換しているのは、新品の紙のようにも見えます。
なぜ「物々交換」に応じたのでしょうか?














