学校に行きたくても行けない「繊細な子どもたち」の不登校についての特集2回目です。
人一倍、敏感な子どもたちは、ハイリー・センシティブ・チャイルド=「HSC」と呼ばれています。繊細さや敏感さが原因で不登校になったHSCの子どもたちの居場所をつくろうと、フリースクールを運営している母親たちの取り組みです。
鹿児島市にあるフリースクール「やさしいハリネズミの楽校 鴨池校」です。
運営する上川知子さん(41)。小学2年と4年、6年と3人の子どもを育てています。3人ともHSCの傾向が強く、宿題や給食、バスでの通学に不安を感じたことがきっかけで学校に通えなくなりました。
HSCは障害や病気ではなく「気質」です。人の気持ちに敏感だったり、環境の変化に不安を感じたりして、子どもなりに頑張ってもある日突然学校に行けなくなる場合があるといいます。
(やさしいハリネズミの楽校 上川知子代表)「人も刺激になるので、人が多いということが刺激になって疲れてしまう。本当は学校に行きたくないけれど、それを言うとお母さんは心配しちゃうかなとか。限界まで頑張って、プツンと切れちゃう子たちが多い」
上川さんは当初、別のフリースクールを利用していましたが、料金は1人月額4万円でした。
(やさしいハリネズミの楽校 上川知子代表)「不登校だから、お金を払って学びにいかないといけない状況は不思議。自分たちで運営するしかないよねと。わが子の居場所があればいいという気持ちで始めた」
同じ悩みを抱える母親たちと、おととし、フリースクールを立ち上げました。鹿児島市の慈眼寺校に続き、去年12月には川内校、今年4月にHSCの子どもを中心とした鴨池校を開校。今では3校あわせて、小学生から高校生まで210人が通っています。
(中学2年生)「学校は団体行動。少しずつストレスがたまり、行けなくなった。ここは自由に遊べて交流もあっていい」
鴨池校は元々、老人ホームだった施設を無償で借り受けました。子どもたちの利用は無料、保護者は初めて利用する前に、3000円の相談料を支払います。施設の光熱費は相談料や企業、個人からの寄付金などでまかなっています。
慈眼寺校と川内校も建設会社からモデルハウスを無償で提供してもらい、3校とも母親などが、ボランティアで運営しています。
HSCの中には集団が苦手な子どももいるため、基本は自由登校です。鴨池校は平日の午後2時から午後5時まで開放していて、学校のような時間割はありません。在籍する学校の授業をオンラインで受けたり、教員免許を持っているボランティアスタッフなどが学習をサポートしています。
子どもたちの中にはハンドメイドの作品を制作し、発表している中学生も。
(中学2年生)「これがおすすめ。一個にギュッと詰まっている感じが自分でもお気に入り」「やっと、自分が来たいところが見つかった。自分のしたいことができるし、周りの雰囲気も全部楽しい」
(中学1年生)「(Q.10年後の自分の姿は?)ハリネズミの楽校みたいな施設のボランティアをして、少しでも子どもたちの居場所をつくれたら。HSCが認められて、普通の世界になったらいいと思う」
文部科学省は2019年、不登校の子どもたちへの支援について、登校するという結果だけを目標としていた方針を転換し、フリースクールなどを活用して社会的な自立を目指すことが大切だという見解を示しました。
しかし、フリースクールの利用料は全国平均で月3万3000円。学習塾などと同じ民間の施設とみなされ、鹿児島では行政からの経済的な支援はありません。全国ではフリースクールへの交通費を助成しているケースはあるものの、ごく一部です。
(やさしいハリネズミの楽校 上川知子代表)「こういう場所が足りない。各地にあったらいい。学校に行かなくても、生きていて笑顔でご飯を食べて、元気に過ごせてたらそれでいい。生きていたらいいと思う。それが一番」
(キャスター)国も「フリースクールなどを活用して社会的な自立を目指す」と方針を転換したとあったが、支援は十分ではないと感じました。
県教育委員会によると、5年前は15か所だった県内のフリースクールは、去年は41か所と3倍に増えました。しかし26か所が鹿児島市に集中していて、いわば地域間格差のような状態にあるのが課題です。
もうひとつの課題が保護者へのサポートです。「ハリネズミの楽校」に来ていた母親に話を聞いたところ、朝も早く起きられるのに、どうして自分の子どもは学校に行きたがらないのか。原因が分からず、孤立した気持ちを抱えていたそうです。しかしHSCやフリースクールのことを知り、気持ちが楽になったと話していました。
(キャスター)自分の子どもが繊細な気質なんだと分かるだけでも、接し方が変わりそうですね。子どもが学校にいけなくなる理由は様々ですが、この連休明けがひとつのきっかけになる場合もありそうですね。
連休明けには、HSCに限らず、子どもたちが登校を渋るケースもあります。保護者はどんな心がけが必要か。専門家に聞きました。
臨床心理士の児玉さらさんです。県教委が県内に87人配置しているスクールカウンセラーの指導役を務めています。
子どもが登校を嫌がるときは、話をよく聞き、休ませる配慮も必要と話します。
(スクールカウンセラースーパーバイザー 児玉さらさん)「学校に行こうと思ったら頭が痛いとか、お腹が痛いと言う子たちがたくさんいる。身体反応が強い間は登校の刺激を与えないことは、一つの視点として大事。身体反応が取れてきたら、今度は部屋からリビングに出られるのか。その時々の状況にあわせて対応していくことが大事」
HSCに限らず、不登校は、子どもたちの心や取り巻く環境でどんな子どもにも起こりえます。今回不登校になった子どもたちを取材しましたが、登校以外の道を当たり前に選択できる社会であってほしいと、感じました。
子どもや保護者向けの相談窓口・「かごしま教育ホットライン24」はフリーダイヤル0120ー078ー310で、相談を受け付けています。
注目の記事
「価格破壊の店」「市民の味方」物価高続く中”10円焼き鳥”守り続ける店主の思い 創業75年の老舗居酒屋 福岡・大牟田市

20歳の娘は同級生に強姦され、殺害された…「顔が紫色になって、そこで眠っていました」 女子高専生殺害事件 母親が語ったこと【前編】

障がい者就労支援で疑惑「数十億円規模」の給付金を過大請求か 元職員が語った加算制度の悪用手口「6か月ごとに契約だけ切り替えて...」 事業所の元利用者も"高すぎる給付金額"に不信感
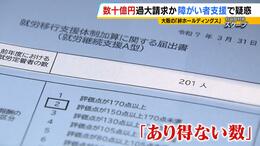
「拾った小石で竹に落書き」「立ち入り禁止エリアに侵入」京都の人気スポット・竹林の小径で迷惑行為が深刻化...記者の直撃にも悪びれないインバウンド客たち 地元商店街からも嘆き「本当にやめてもらいたい」

“ニセ警察官”から記者に詐欺電話「保険が不正使用されている」だまされたふり続けると“事情聴取”も…【特殊詐欺手口の全貌】
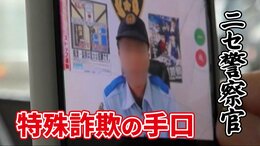
15年前の“時効撤廃”なければ逮捕されることはなかった 安福久美子容疑者(69) 別事件の遺族は「ぱっと明るくなりました」 全国には未だに350件以上の未解決事件









