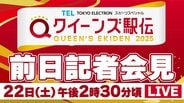高野コーチが見た山縣の動き
しかし復帰戦の山縣は、持ち味のスタートで左隣の桐生に大きく置いていかれ、中盤以降も巻き返すことができなかった。10秒48(+0.5)は雨が降っていたとはいえ、日本リストなら昨年のシーズン142位相当。「隣に桐生君がいて、他のライバルもいる中で走るのは難しかった」という。練習ではできていた動きを、極限スピードを出すレースで再現することができなかった。

山縣本人はレース後半のリズムが良くなかったことを強調した。「50m以降の走りがバラバラになったのは、レースから遠ざかっていた影響もあるんだろうな、と感じました。スパイクを(厚底に)変えて、自分の中で決めていたリズムとは、特に中盤以降はバラバラになってペースがすごく乱れました」。
股関節で地面を捉える動きはどうだったのか。高野大樹コーチは実戦の動きを次のように見ていた。
「大きく崩れていないと思います。ヒザに痛みが出ていないこともその現れです。ただ、スタートで関節が深く曲がる局面での力の出力が低かった」
それがスタートで遅れた理由にもなるが、中間疾走に関しては「ケガの前よりも股関節を意識した走りはできていた。ダイナミックさを出せるようになった」と見ている。
ただスパイクとも関連する部分で、一概に断定はできない。
そして山縣が大会前日に課題としていた、加速局面から中間疾走への切り換えに関しては、「できていたと評価するのは難しい」と言う。後半、リズムに乗らなかったことの一因だろう。
前述のように練習で確認できている動きでも、トップスピードを出すレースで再現するのは簡単なことではない。だがスピードが若干遅くなる200mなら、再現できる可能性が高くなる。
3月20日の取材で山縣は、次のように話した。
「今は技術練習にも時間をかけて、新しい体の使い方を習得中です。いかに定着させていくか。一生懸命に走る100mではなく、リラックスして考える時間がある中で走る200mの距離から取り組むことが重要になります。23年は技術を高いレベルで定着させて、その土台がある中で24年は100mで思い切り体を動かしていく」
100mと200mのわずかのスピードの違いで、動きの意識できる範囲が違ってくる、ということだ。
しかしその200mでも、できる限りのスピードを出さないと100mにつながらない。織田記念前日にも「200mを中心に取り組んできたので、明日の100mで刺激を入れて、木南記念(5月7日)の200mにつなげていく」と話していた。
「世界で戦うためには自己記録(20秒41)を上げていきたい」とも語った山縣。世界陸上ブダペストの参加標準記録は20秒16と高いが、まったく不可能という数字ではない。
山縣は18年以降、200mにはほとんど出場していない。20秒41の自己記録を出したのは奇しくも、桐生との戦いが始まった13年である。30歳の山縣が10年ぶりに200mの自己新を出せば、極めて大きな意味を持つ。
(TEXT by 寺田辰朗 /フリーライター)