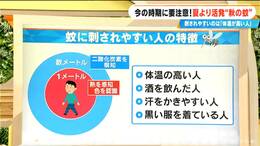「誰かを大切にしようとすると後回しになる人も」
ホラン千秋キャスター:
どのようなライフスタイルを送っているかによって、意見が分かれそうですね。
若新雄純 慶応大学特任准教授:
僕らの生活はテクノロジーによっていろいろ楽になったことは多いと思いますが、小さな子どもを外に連れて行くことに関してはテクノロジーで簡単になった部分はほとんどないと思いますね。突然泣き出したり、ぐずったり、体調を崩したりするのはテクノロジーでカバーしきれない。それぐらい人間の命を育てていくってことが難しくて大変なこと、だけど尊いってことだと思うんですよね。
一方で、子どもを産まない・持たない選択をしてる人たちは全然優遇されない社会じゃないかっていう話になってくると思うんですけど。
誰かを大切にすると、そうじゃない人たちは後回しになりますよね。そこを選んでいくのが、国・政治がやることだと思うんですよ。別に僕はこれが一番って言いきりたいわけじゃなくて、国が何を今一番にするのかという方針をちゃんと見せているかどうかだと思うんです。
『子どもファースト、子育てファーストで完全に行きますよ』って、国がそこまで宣言しきってない気がして。『子どもファーストにしてみようと思うんですけど、どうでしょうか皆さん』って空気を読んで、国民が『それでいいんじゃないの』ってなってきたら、そうですよね、子育てが第一ですよねって後で言おうとしている雰囲気があって。
ちゃんと方針を発表すれば、あとは納得いかなければ選挙で結果が出ると思うし、そういう潔さがちょっとない気がします。
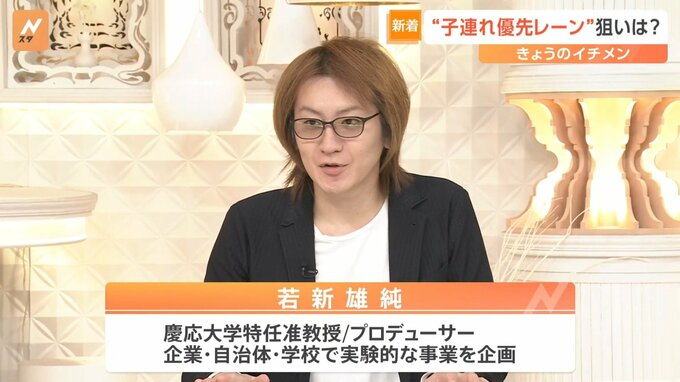
ホランキャスター:
全ての方が満足する政策って難しくて、何かをやるには何かを犠牲にしなきゃならないという部分もありますね。
若新雄純 慶応大学特任准教授:
そこを国民の反応を見てから最終的な方針を決めようとする、日本のムラ社会っぽいやり方だと思うんですけど、そこはちょっと歯がゆいですね。