歴史を物語る集落も…消えゆく引揚者の足跡

大阪・貝塚市に、引揚者たちを公費で受け入れた集落、「東貝塚住宅」がある。この場所で生まれ育った村崎太さん(55)。母親の節子さんは満洲からの引揚者だ。引揚者住宅の中を見せてもらった。
木造平家建て、6帖の居間と3帖の寝室。そして台所。トイレは汲み取り式だ。家賃は月額360円だという。

村崎太さん
「近隣からの差別もありました。『あそこはあんまり行ったらあかんよ』とか耳にしました。引揚者=貧しい。そんなふうに思われてたんじゃないですか。貧乏人の集まりやと。実際は、母もお金の面で苦労したりしてましたけど、子どもにはそういう仕草は一つも見せなかった」

ここに住む者同士、助け合って生きてきたという。
全国に7万9000戸造られた引揚者住宅だが、老朽化などで解体が進み、現在はほとんど残っていない。この集落には最大50戸ほどの住宅があったというが、現在は3戸を残すのみとなっている。
5年前に母親が亡くなり、引揚者住宅に住む権利を失ったとされ、この取材の翌日までの立ち退きを命じられていた。

村崎太さん
「大阪府の条例は同時期に入居した子供には住む権利を認めるが、後から生まれた子供には認めないと」
――でもここの引揚者住宅の集落というのは、生きるか死ぬか潜り抜けてきた人たちがたどり着いた安住の地ですよね?
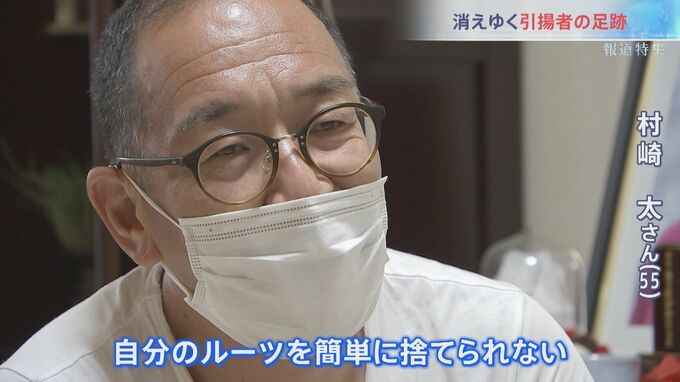
村崎太さん
「(この場所を)残したいんですよ。ここが僕のルーツなんです。自分のルーツは簡単に捨てられない」
歴史を物語るこの場所を残したい…そんな思いは叶わなかった。

母親のお気に入りだったという大きな絵画は、ギリギリまで居間に飾っておいた。
――お母さん、なんで気に入ったんだろう?
村崎太さん
「引き揚げのことと被るそうです。この道はいろんな方がずっと通ってできた道っていうんで、いろんな方が通るってことは、いろんな人の思いがこの道にはあるっていう。そんなふうに母は思ったんですね」
そして、翌日…
――おはようございます。いよいよ最後の朝、どんなお気持ちですか?
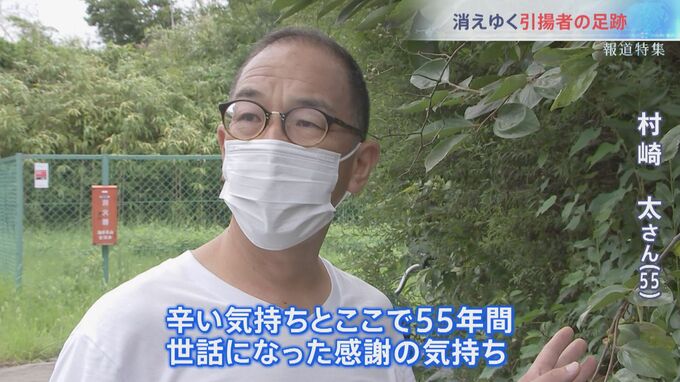
村崎太さん
「辛いです。辛い気持ちとここで55年間、お世話になりましたので、感謝の気持ち」
最後に玄関の表札を外した。
村崎太さん
「もう読めないですね。『村』と辛うじて、『崎』がわかるのかなっていう。これだけ長いこと住んでたという」
家は大阪府に明け渡された。秋にも取り壊されるという。
――引揚住宅とか、もしかすると将来的には引揚者というものを忘れ去られてしまうかもしれませんね?
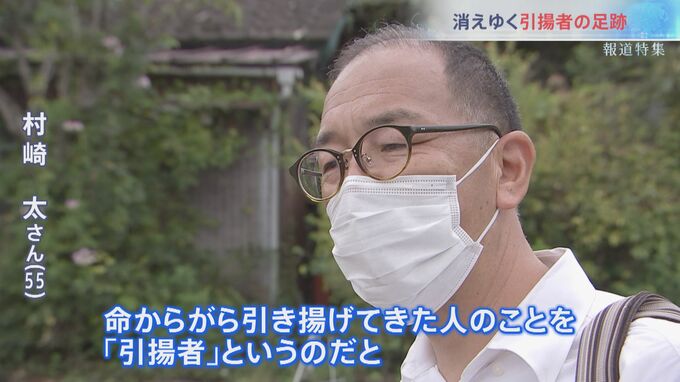
村崎太さん
「『引揚者』って言葉、若い記者の方は知らなかったです。『引揚者ってどういうことですか?』と。戦前に満洲へ日本が行き、大戦に負けて、命からがら引き揚げてきた人のことを『引揚者』っていうんですよって」














