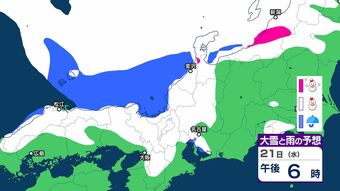高齢化社会が進むにつれて、「嚥下障害」の方も増えています。「嚥下」とは人の体が食べ物や飲み物を噛み砕いて飲み込み、喉から食道、胃へと送り込むはたらきのことで、これが上手くできないのが「嚥下障害」です。最近では、嚥下障害の方でも食事が楽しめる飲食店が増えています。さらに、そうした飲食店を紹介するサイトも登場しています。今回は、そのサイト「嚥下食レストラン.jp」を取材しました。
嚥下障害のある人も、家族や友達と外食したい
嚥下障害があると、健常者と同じ固形食を食べるのが難しくなりますが、そうした人たちが食べやすいよう、料理を柔らかくしたり、小さく刻んで飲み込みやすい状態にしたものが「嚥下食」です。
ただ、「嚥下食」を常時提供する店はまだまだ多くなく、障害のある人たちが外食する障壁になっています。
そこで、障害者が家族や友達などと一緒に、美味しい外食を楽しめる飲食店や宿泊施設約40軒を紹介しているのが「嚥下食レストラン.jp」というサイトです。2年前にこのサイトを作った齋藤匡布さんはこのように言っています。

「嚥下食レストラン.jp」齋藤匡布さん
「嚥下障害の人は、ふだん病院でまずいものを食べさせられているわけです。ところがそういうレストランに行くと、ハードルがあがるんですけど、気持ちもあがってくるので、いつも食べてるものよりも、食べられるようになるものなんですよ。いつも食べてるものは味気ないじゃないですか。それに対して、レストランなどに行って味があるものを食べると、すごく喜んで食べられるので。食に対する意欲はものすごく強いと思います。家族と一緒に出かけたいという思いが嚥下障害の人でも強いのですが、ただ、嚥下食が必要な高齢者や障害者が食べられるものがない場合があるんです。そういう時に家族の方と一緒に食べられるような嚥下食レストランは全国にどのくらいあるのか、みなさん東京にいるわけではなく、地方在住の方もいるので、そういう人たちに向け、家族で食べられるようなレストランガイドができたらいいなと思ったのが『嚥下食レストラン.jp』を作るきっかけになりました」
医療と飲食店のコラボで「誤嚥性肺炎」のリスクを減らす
齋藤さんは以前勤務していた病院で、嚥下障害のある人が「どうしてもフライドチキンが食べたいけれども、食べられない」という強い思いを持っていることに接し、それをきっかけに嚥下障害の専門治療や支援に携わってきたそうです。
嚥下障害のある人たちは食べたものが食道ではなく気管に入ってしまい、口内細菌が肺まで入って肺炎を起こす「誤嚥性肺炎」という重い症状になる場合があります。齋藤さんは、普段は訪問医療などをする歯科医をしながら「日本誤嚥性肺炎予防協会」という会を5年前に立ちあげ、その予防や認知度の向上を目的とした活動もしています。齋藤さんに「誤嚥性肺炎」について聞きました。
「嚥下食レストラン.jp」齋藤匡布さん
「誤嚥性肺炎って一度起こしてしまうと、何度も何度も起こしてしまうんですよ。誤嚥性肺炎になった人が2年以内に死亡する確率は8割とか9割とかいわれてるぐらい怖い病気です。ですから、摂食嚥下障害の人がいかに誤嚥性肺炎を起こさないか。それがその人の寿命に関わってくる。誤嚥性肺炎という言葉はだんだん認知されているんですけど、そこに大きな原因の『摂食嚥下障害』という言葉がついてきてない、というのが現状なんですよ。レストラン側にしたら、嚥下食を作る技術はあったとしても、医療的な裏付けがないから、怖くて提供できないケースが多いんです。なので、『嚥下食レストラン.jp』がもっと目指さなきゃいけないのは『レストランを紹介したから終わり』じゃなくて、そこにしかるべき医療機関がついて、『こういうものだったら提供できる』という情報提供をして、医療と飲食店がうまくコラボできる体制を作っていくことかなと思っています」
一度誤嚥性肺炎を起こした人は、食べることに抵抗や恐怖を感じてしまい、食欲がなくなり、体力が落ちてしまうこともあるそうです。こうした誤嚥の事故やリスクをなくすためにも、サイトを通して嚥下食を広め、身近なものにしたいと齋藤さんは言っていました。
「嚥下食レストラン.jp」では和食、中華、フレンチなど料理のジャンル別や店がある都道府県で検索できるようレイアウトされています。嚥下食を出せる店の情報は無料で掲載しているので、興味のある方や「嚥下食を出している」というお店の方はぜひアクセスしてみてほしいと思います。