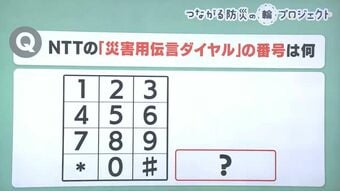防寒具は撤去された 何事もなかったようにいつもの日常に
ほどなくして3体の防寒具は、岡山市中区役所地域整備課により取り除かれることとなった。課によると「善意だと思うので心苦しいが、無届けで着せるのはやはり望ましくない。撤去はやむをえない」という結論に至ったという。
市民の財産である像の、本来の芸術的価値を守るための苦渋の決断と言ったところか。傷つけられたわけではないので被害届けを出すような事案でもない。行政も対応に相当頭を悩ませたようだ。

実際に石山公園の像を見た県外の観光客からは、「けしからん」というメールが寄せられたという。
行為者の意図はともかく、今回の着衣像はいわば平穏な日常に、ある朝突然出現したとても小さな違和感であり “さざなみ” だ。マイノリティの行動とも言えるだろう。こうした行為に対して大衆はどう反応するのか。多様性を尊重する社会に向かう今、とても興味深い。

桃太郎像がはじめに独白したとおり、街ゆく人々はほとんど関心を示さなかった。海外を転々とし、岡山に引っ越してきた2人の友人(ある意味で地域のマイノリティだ)が、岡山を気に入っている理由の1つとして口を揃えた印象的な表現がある。岡山の人は「適度な距離を置いてくれる」と言う。
無関心なのではなく、無関心を装ってくれるのが心地良いのだそうだ。それでいて、いざ何かを相談しようものなら、あたかも事前に準備していたかのごとく熱心に関与してくれるのだと言う。
何が言いたいのかというと、着衣像を目の当たりにした人々は「無関心を装って通り過ぎただけなのではないか」ということだ。リスク管理のためいったん距離を置いて他の誰かの反応を待つが、実は事の顛末がどうなるか、面白がって見守っているのではないか。
このマイノリティの行動への関わり方は、「同調圧力が指摘されている日本の社会」が「多様性を重んじる社会」に成熟していくステップにおいて、非常に多くのことを示唆している気がするのである。
さて、少なくとも岡山の街ゆく人々は、防寒具が撤去された後も何事もなかったかのように収束を受け入れたように思えた。ところがだ。すっかり日差しが春めいた3月上旬のある日、交差点の桃太郎像を見て驚いた。


しっかり、新たなニット帽子を被せられているではないか。令和の「笠地蔵」の物語はまだ終わらないようだ。