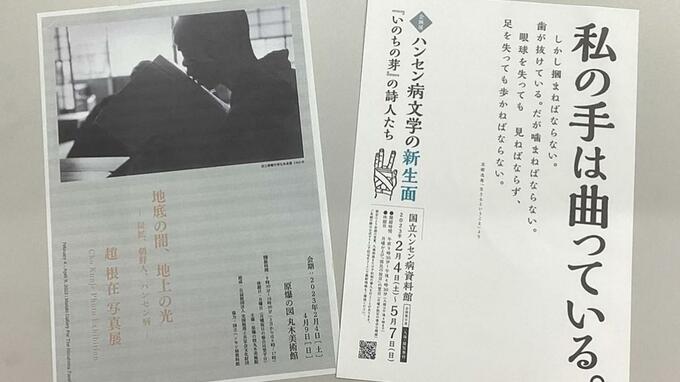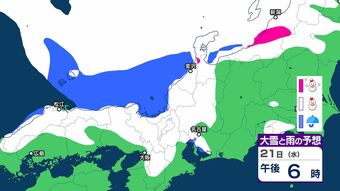国立ハンセン病資料館で開かれている「ハンセン病文学の新生面 『いのちの芽』の詩人たち」と、原爆の図丸木美術館で開かれている「趙根在写真展 地底の闇、地上の光 -炭鉱、朝鮮人、ハンセン病-」の2つの展示を、今回取材しました。
「いのちの芽」から読み取れる意味
タイトルにある「いのちの芽」というのは「詩集」のタイトル。戦後の1953年、今から70年前に、8つの療養所から73人が参加して編まれた詩集です。

強制的に隔離された療養所の中では戦後、日本国憲法が基本的人権をうたい、プロミンという治療薬が使われるようになったことを背景に、文学にも新しい表現が生まれます。
展示を企画した学芸員の木村哲也さんは「療養所に閉じ込められて、自分たちの境遇を宿命として諦めるっていう、戦前のそういう意識から抜けて、自分たちの未来というのは、変革可能なんだってことを考える人たちが戦後になって、現れます。戦前のハンセン病文学にありえなかった、意識の変化だと思うんです。そこを企画展のタイトルにうたっています」と説明します。
そして、「資料館は、いわゆるハンセン病問題、人権学習の場であるんですけども、今回は、詩を通して、そういうことを知る糸口になったらといいな、と思っています」と話していました。

展示では、「いのちの芽」の中の25の作品や、その作者について、わかっている範囲の経歴や、編者を務めた詩人の大江満雄と、参加した人たちがやり取りした手紙など、貴重な資料も見ることができます。