新潟県三条市で2024年3月1日に開院する県央基幹病院。県央地域の救急患者を地域内で診ることができず地域外へ搬送するケースが多く、また搬送時間も県内平均よりも長くなっています。こうした現状は県央基幹病院の開院でどう変わるのか。“断らない救急”を目指す「ER救急」の導入を前に、燕労災病院(燕市)では2022年4月から「プレER救急」を開始。見えてきた成果と課題は…。現在燕労災病院の病院長で、県央基幹病院の病院長に就任を予定している遠藤直人さんに開院1年を前にインタビューを行いました。
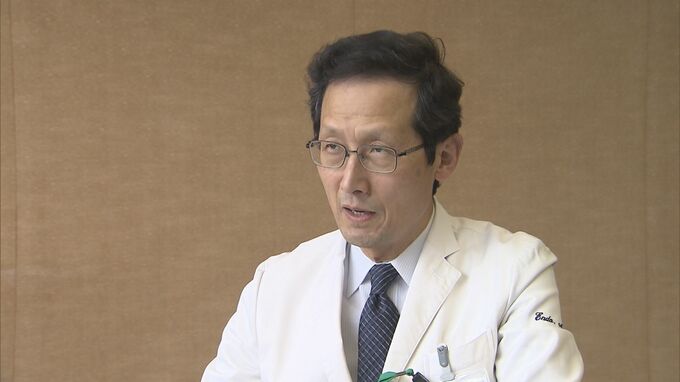
ー県央基幹病院のコンセプトを教えてください
コンセプトは大きく言えば県央地域の患者さんを、この県央地域で診るということです。というのは例えば今の救急医療を見ると、ここの救急患者の4分の1はこの地域で診られずに新潟市や長岡市に運ばれているという現実があります。まずこれを解決するという観点から、県央地域の患者さんを県央地域で診る。これをコンセプトの第1にしたいというふうに思っています。

ー県央基幹病院が開院すると、どう変わるのでしょうか
大きく二つ私どもが目指してるところがあります。一つは今お話しましたように救急ですね。県央基幹病院という急性期の集約した医療ができるところがありますので、まず県央基幹病院にお願いすればいいというルートができるわけですね。まずそこに短時間でアクセスすることができるということになりますので、救急隊の人にとっても搬送時間の短縮に繋がりますし、患者さん・ご家族にとっても不安なくまず診てもらうところに行けるという安心感を抱くことができるんじゃないかというふうに思います。
もう一点は、今後の医療を見据えたときに高齢者の医療だと思うんですよ。今人口はこの地域で22万人弱ですけども、今後総人口としては減っていきます。しかし75歳以上の高齢者の方、いわゆる後期高齢者の方は減りません。今後増えていきます。そうすると高齢期、特に後期高齢者の医療需要は今後も継続してある、むしろ増大するということになるわけです。それを見据えて今から準備対応していくことが必要だろうというふうに考えます。そうすると県央基幹病院、それから周辺の病院と連携を組むことによって来る高齢者医療の需要増大に対応できることになるんじゃないかというふうに考えています。

ー人材育成にも力を入れているとお聞きしました。
人材育成については、残念ながらここ若い人いないんですよね。医師、それからスタッフも含めてですね。ですからもちろん喫緊の課題として今働いていただく方が欲しいです。医師もメディカルスタッフも。しかしそれは今欲しいだけであって、今後長続きするわけではないわけですよね。そうするとやっぱりこの地域で“次世代を担う方々”を育成していくことも重要だろうと思うんですね。ただしここで人材育成をするから、ここに引き留めておこうというような考えではなくて、ここを一つの足がかりにしてここで研さんを積んでいただいて、県内の各地域あるいは県外の方に羽ばたいていってほしい。そうすることによって県央地域の医療をほかに伝えることができますし、また新たな方々の人材の関心を引くこともできるんじゃないかというふうに思っています。ですから人材育成とここを契機にして羽ばたいていくという人を作っていきたいというふうに思います。

ー複数の病院の機能を集約して、県央基幹病院を作るというプロジェクトは珍しく、注目されている部分あると思いますが
注目していただいてるのはとてもありがたいことですけど、考えただけで頭が痛くなるほど困難で複雑な問題です。よく言われるんですけど、そもそもこの経営母体の違う組織が一緒になりますよね。それ以外の病院のいわゆる急性機能を集めてくるわけですよね。そして新たに人材を入れるわけですよね。そうしないと大きな組織になりませんので。そうすると非常に複雑にいろんな方々が混在する組織ですよね。そして今の医療をやればいいんじゃなくて、今よりも高いレベルの医療、それから今後必要な医療を対応していくような体制を作ろうとしてるわけですから、みんなが学んでいかなければいけないわけですよね。それを考えただけで一つの組織にするということ、それからみんなが知識や技術を身につけていくこと。その大変さっていうことが頭が痛いでしょうかね。でもそれをしない限りはやっぱりいい病院、いい医療体制になりませんので。困難ですけども、そういったことを目指してきたい。ですから、先ほど人材育成って話がありましたけれども、こういった困難な事業。しかし魅力ある事業。こういったものに挑戦する気持ちを持った方々、そしてもう一つはいろんな病院と連携を図らなきゃいけませんので連携をする。そして医療の現場っていうのは医師、看護師、その他メディカルスタッフの方など大勢の職種の方がおられますので、そういった職種の方々とのコミュニケーションを取れるだとか。あるいは患者さんご家族とコミュニケーションが取れるとか。そういった連携する力、会話する力があるか。そういったことが必要じゃないかというふうに思っています。
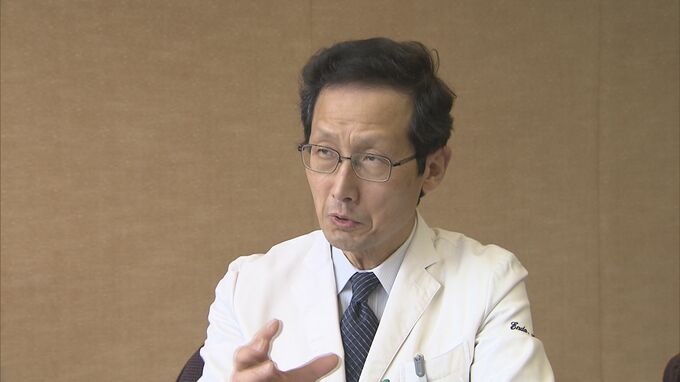
ーER救急、“断らない救急”で集まった救急患者をどこに繋いでいくかというところが一つ課題になってくる。他の病院との連携について教えてください。
救急患者を受け入れるということは受け入れるキャパシティが必要ですよね。受け入れるキャパシティは今、病院の中にいる人が出ない限りはキャパシティは生まれないんですよ。勝手にどんどん増えていくことはないので。その方々を在宅自宅か、あるいは転院をしていただくことが必要なわけです。そうすると転院は、近隣のいわゆる地域密着型病院あるいは民間の病院、あるいはそういった施設等にお願いすることになるわけですね。ここのところの連携をやっぱり密にすることが大事だろうというふうに思います。それでこれについては早くから必要性がわかっていましたので連携室会議というものを、この地域ではやっています。そしてまたそれをサポートするようにこの県央地域の病院長の会議も毎月やっています。病院長が院内の意見をある程度サポートしていただいて、実際の実務は連携室がするわけですので、連携室のところで会議をしながらこういった事例のやり取りはどうしたらいいかとか、今やってることについて問題点はどうかとか、あるいはより円滑にするためにはどうすればいいかっていうことを今やり取りをしているところです。まだまだ途中ですけども、こういった関係をより続けていって少しでもうまく円滑に繋げることができればなというふうに思ってるところです。

ー開院まで残り1年。今後の展望についてどう考えていますか。
期待が大きくて本当に汗が出るぐらいの思いですけど、まずやっぱり建物は順調に建っていますので、まず組織作りですよね。やっぱり人が非常に重要ですので、人を集めて育成する。そして必要な知識技術を身に付けていく。こういったことが必要だろうというふうに思います。ですから人を集めることについては県内外含めて発信をして、できるだけ多くの方に関心を持っていただくようにしています。そして、いろんな教育とかをしていく必要がありますので、それは院内でも、あるいは近隣のところを含めて、それからここにない機能も今度、新しい病院には加わってきますので、そういったものも皆で学んでいこうということを今しているところです。

ー院長予定者になるにあたってプレッシャーはないのでしょうか。
どう考えたって難しい問題ばっかりじゃないですか。人集めにしろ組織作りにしろ、それからここの病院だけじゃなくて他の病院の方向性、機能についても検討していかなければいけない。一方で、各市町村から、あるいは患者のいろんなグループ、患者の会からも要請・要望があるわけですから、なかなかそれを考えるだけで頭いっぱいというか気が重い感じになりました。ただこの地域でやはり医療が困ってるということは事実ですので、それを少しでもお手伝いできればという思いですね。














