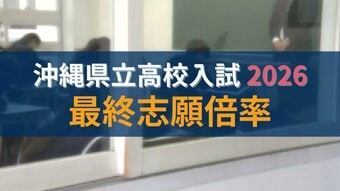深く日本を知るために求められる日本遺産ガイドとは
地域の歴史や、受け継がれる伝統を、1つひとつの点ではなく、関連性をもって伝え、より深く日本を知ってもらうことにつなげる。そのための知識を備えたガイドの育成は、観光庁が全国で力を入れている『日本遺産』制度の取り組みの1つです。
これまで国内観光客向けのガイドには研修が行われていましたが、外国語を使うガイドについては今回が初めてで、この研修で県内には18人の『日本遺産ガイド』が誕生する予定です。
一行が次に訪れたのは泡盛の酒造所、瑞泉酒造。
販売員「戦争さえなければ、100年もの200年ものがあったといわれております」

琉球泡盛は“守礼の邦”のおもてなし文化を構成する要素として『日本遺産』に登録されているものの1つ。参加者はアジアとの交易によって伝わってきた歴史などを詳しく学びました。

参加したガイド「3年おいたら古酒になるとか、今は泡盛だけじゃなくて梅酒とかもあると。中華圏の観光客に関しては結構アピールできる(ガイドとして)と思います
参加したガイド「海だけでなくお酒の文化、歴史、深い文化を掘れば掘るほど面白いと思ってますので、この気持ちを伝えていきたい」
モニターツアーの最後には、伝統の琉球料理に舌鼓。琉球王国が国賓をもてなした『御冠船料理』も日本遺産に登録されていて、ガイドたちにとってはここも学びの場です。
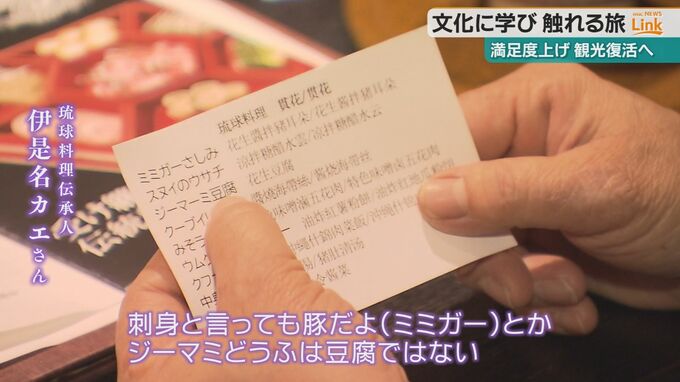
琉球料理専門家「刺身と言っても豚(ミミガー)だよとか、ジーマミどうふは豆腐と言っても豆腐の材料入ってないとか、『沖縄の人は普段からこういう食事をされますか』とか、そういう質問されるはずですと説明している」
歴史・工芸・料理。様々な沖縄の魅力とそのストーリー性に触れた参加者の満足度は高かったようです。
観光客の女性「琉球文化・歴史について勉強になり、そして琉球舞踊を鑑賞しながら、特色のある琉球料理を体験することができてすごくうれしい。中国と日本がさらに平和な関係になり、より多くの観光客が沖縄を訪れ、沖縄・海・食の美しさを体験してほしいと思います」
これから本格的に戻ってくる中華圏からの観光客。より深く沖縄を知ってもらおうとする受け入れ態勢づくりが進んでいます。
【記者MEMO】
今回のモニターツアーには39人が参加しましたが、県内には、中国語通訳案内士は337人いるということです。より深い知識を持った高いレベルのガイドはまだ増えるかもしれません。沖縄の様々な魅力が中華圏に発信されて交流が深まることを期待されます。