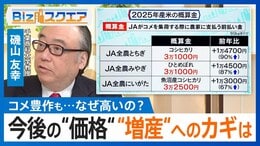■「日銀が市場に屈した日」
日銀がようやく異次元緩和の修正に踏み込みました。これまで日銀は、10年の長期金利の上限を0.25%から0.5%へと拡大したのです。その結果、決定後には長期金利が一時0.48%にまで跳ね上がりました。今後、固定の住宅金利や企業への貸出金利も上昇するので、目の前にある事実は、「金利の引き上げ」に他なりません。今回の政策修正は、異次元緩和の「終わりの始まり」です。
実際、日銀は追い込まれていました。世界的な金利上昇を受けて、日本の長期金利は0.25%に張り付いていました。日銀は、それを抑え込むために、大量の国債購入を余儀なくされました。最近は取引が成立しないケースも増えていました。どこかで修正せざるを得ない状況だったのです。ウォール・ストリート・ジャーナル紙は、この修正を「日銀が市場に屈した日」と評しています。
■市場の裏をかくことが最大の狙い
では、なぜ今、修正に踏み込んだのでしょうか。最大の理由は「市場の裏をかく」必要があったからです。金利がこれだけ長期にわたって人為的に抑えられていれば、いったんタガが外れれば、金利は急騰してしまいます。長期金利の上昇(逆に言えば、国債価格の下落)を予想するエネルギーが、マグマのように溜まっているのです。
円安が150円台まで進み、市場が利上げを催促する中では、到底できないことでした。事前に修正観測が広がれば、決定直前に日銀は膨大な国債を買わざるを得ない羽目になるからです。投機筋を儲けさせるような政策変更は、やりたくなかったのです。円相場が円高方向に戻って市場の警戒感が薄れ、欧米の市場関係者がクリスマス休暇入りした閑散期だからこそ、政策修正は可能だったと言えるでしょう。
■米景気後退と日銀総裁人事も絡んで
今後に目を転じると、アメリカの利上げが終盤に近づきつつあります。アメリカの金利が天井を打ち、引き下げに転じてしまったら、日本が引き締め方向に修正することは、なかなか難しいでしょう。アメリカの金利が上がっているうちに踏み出す必要がありました。
また、来年春には黒田総裁の任期切れを迎えます。新しい日銀総裁に一定の柔軟性(といっても極めて限定的ですが)をもって引き継ぎたいという思いも、黒田氏にはあったことでしょう。異次元緩和で「とっちらかした」まま立ち去ったとは、言われたくない、という美学です。いずれの点からも、この12月がラストチャンスだったと言えます。
■物価上昇が緩和修正を可能にした
今回の記者会見で黒田総裁は、準備された公式見解を繰り返す場面が目立ちました。自分の言葉で語った数少ない発言が、「インフレ率が上がっているので実質金利はむしろ下がっている」と反論したシーンでした。黒田総裁は公式には、来年度には物価上昇率は落ちていくとの公式見解を維持しつつも、2%達成の可能性が高まっていると見ていることが、垣間見える場面でした。物価上昇に自信を深めているからこそ、長期金利を引き上げることが可能だったのでしょう。
■あり得ない『織り込み済み』、「不意打ち」の必然
とは言うものの、今回の緩和修正は、多くの市場関係者にとっても、私にとっても、恥ずかしながら、全く寝耳に水でした。黒田総裁自身が「変動幅の拡大は利上げにあたり、適切ではない」と直前まで明確に否定していたからです。でも、当然、想定すべきことでした。
今回、はっきりしたことは、異次元緩和の出口、とりわけ長期金利の目標変更や撤廃を、事前に「織り込み済み」にさせることなどあり得ないということです。「織り込み済み」になったとたんに金利上昇圧力が高まってしまうからです。異次元緩和の出口は、いわば「不意打ち」であることが必然なのです。
だとすれば、完全な出口までの長い道のりでは、日銀こそが、世界の金融市場の最大の不安定要因になると、言えるのかもしれません。
播摩 卓士(BS-TBS「BiZスクエア」メインキャスター)