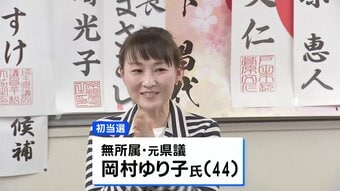■耳を疑った、復興増税の『転用』
最初にニュースを聞いた際には、耳を疑いました。岸田政権と与党が、防衛費大幅増額の財源として、復興特別所得税から、その一部を転用することを検討しているというのです。東日本大震災からの復興のためと説明して行った増税を、防衛費対GDP比2%実現のために『流用』するようなもので、筋違いも甚だしいと思ったからです。
復興特別所得税は、東日本大震災の復興財源を手当てするための2013年から2037年までの25年間にわたって、所得税額の2.1%を上乗せ徴収しているものです。所得税を払っている人すべてに課せられているというのが特徴で、国民が皆で被災地の復興を支えようというのが、その趣旨です。この一部を防衛費に充て、復興財源が足りなくなる分だけ、増税期間を延長しようというものでした。
■『防衛新税』に看板架け替え、実態は『転用』と変わらず
『転用』があまりに不評だったので、1%の『防衛新税』と看板を掛け直しましたが、その分、復興増税は所得税額の1.1%に縮小されるという枠組みはそのままです。2024年から新税が導入された場合、延長期間は13年になるとの見通しです。表面上、1年あたりの負担額は変わりませんが、特別な増税期間が13年も長くなるのですから、紛れもない所得税増税です。何と姑息な発想でしょう。
■防衛費は期間限定の目的税で賄うのか
そもそも防衛費を目的税で賄うのはおかしいでしょう。国防は国家のありようそのものですから、恒久的な一般財源で手当てすべきものです。警察目的税や消防目的税が次々出来たら、それこそ大変です。
期間限定の付加税は、震災復興のように、臨時的に発生した歳出を賄い、目的を達したら終了、というのが、本来のあり方です。防衛費の増額は、国際情勢の構造変化を受けたものですから、10年経てばGNP比1%に戻るといった性格のものではありません。防衛費増額の財源が足りないのであれば、所得税や法人税の増税を正々堂々と提案し、選挙で国民の審判を受けるべきなのです。
■増税の既成事実化が目的なのか
今回の防衛費増額にあたっては、必要な防衛の中身の議論よりも、財源論が先に走り過ぎました。岸田総理がバイデン大統領に大幅増額を約束したことが発端で、まずGDP比2%という「数字ありき」で議論が進められました。5年間で総額43兆円の防衛費が必要で、27年度には1年あたり4兆円の歳出増になるという説明です。その4兆円のうち、①歳出改革、②剰余金の活用、③税外収入による防衛力強化資金などで3兆円近くを賄うものの、残る1兆円強は増税が必要になるというのです。なんと大雑把な計算でしょうか。
今回、所得税の付加税として導入を目指す『防衛新税』の歳入見込みは、年間およそ2000億円。他の3つの項目が上振れすれば、必ずしも吸収できない数字ではありません。「防衛費増額には所得税増税が必要だ」と示す、政治的意図が透けて見えます。政府にとっては、今後の様々な歳出増加圧力を睨んで、まずは所得税増税という既成事実を作ることこそが最も重要だったのではないか、と勘繰りたくなります。
■増税の際にやるべきこととは
防衛費増額という巨額の歳出増加には財源の手当てが必要だ、という議論は、その通りです。しかし、その際にやるべきことははっきりしています。まず、増税の前に、他の歳出見直しなど、やれることはやること。そして、増税がどうしても必要なら、国民にきちんと説明して理解を得ることです。
所得税増税はすべての国民に影響を与えます。今回の防衛新税は約束違反満載で、とても国民の理解は得られそうにありません。