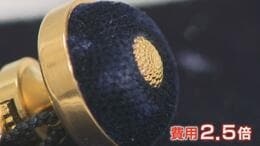千差万別の苦しみがあった
(米澤秀敏記者)
「2016年から2019年の取材です。つい最近のことです。ようやく、家族の皆さんが勇気を持って告白されたということなんです。原告の方が岡山にいましたから、私もお話を伺うことができました。実名で、顔を出して証言してくださる方は、ほんのわずかです。
568人の集団訴訟です。国の強制隔離政策がもとで、ハンセン病の元患者の家族もまた差別と偏見にさらされたとして、国に謝罪と損害賠償を求めた裁判です。
ハンセン病の患者とされた人の子、また、発症時に同居していたご家族ですね、兄弟、姉妹、配偶者、親、孫、甥、姪、そういった方々でした。20代から90代まで、九州、沖縄が半数以上、そして中四国など、全国、そして海外にも原告がいらっしゃいました」

「原告団副団長の、黄さん。とても仲睦まじい家族の写真がありますけれども、これを撮影してまもなく、家族は引き裂かれてしまいました」

黄さんは1歳で、岡山市の育児院に預けられた。お母さんと下のお姉さんが長島愛生園に、さらにその1年後には、お父さんと上のお姉さんも入所しました。
黄さんが9歳の時に、4人が園を退所して、育児院に迎えに来るんですけれども、黄さんには1歳の時から8年間、楽しかった記憶しかないんですね。突然『私たちが家族です。一緒に住みましょう』と来るという。
『逆に閉じ込められたみたい』とおっしゃっていましたが、家族の関係性が、隔離政策によって根こそぎ奪われてしまったことが被害だと、黄さんは訴えてこられました」

「原田さんの場合は、自分の家に消毒に来られたことで、家族がハンセン病だったということが明るみになった。家の布団が燃やされたり、家が真っ白になるほど消毒されたり、そして、お母さんと2人暮らしになるわけですけど、お母さんは仕事もクビになって、食べていくことがままならなくなって、一緒に死のう、死のうと言われた。原田さんの中に強烈に残っている出来事なんですね。そういった千差万別の被害がこの家族訴訟にはありました」
「黄さんは、意見陳述で法廷に立ち、涙ながらにご自身の思いを訴えました。裁判後の会見で、私は黄さんに涙の意味をたずねました。
『自分が一番辛いことを話さないと、伝わらないんじゃないかと思った』とおっしゃいました。強く印象に残っています」