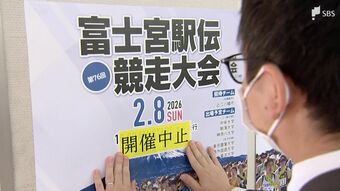災害が起きたとき、自力で逃げるのが難しい人たちの安全確保は重要な課題です。迅速な避難につなげるポイントは、支援する人や避難場所をあらかじめ決めておくことです。
10月下旬、静岡県富士市三四軒屋区の公会堂に、町内会の役員や民生委員、福祉関係者たちが集まりました。地域には、災害時に自力で逃げるのが難しい高齢者がたくさんいます。どのように支援して安全を確保するか計画を立てていました。
<打ち合わせの様子>
「何か必ず持っていかなければならない必需品は?」
「薬がないと症状が悪化する」
85歳の母親の足が不自由だという寺田江身子さんです。ケアマネージャーと一緒に母親の状況について説明しました。高齢者や障がい者など、避難に支援を必要とする人はたくさんいます。ただ、病気や障がいの状況はもちろん、生活環境も違うため、100人いれば、100通りの避難計画が必要です。
<打ち合わせの様子>
「横断歩道などがあるのは?」
「ない、ここだけ」
「ここは信号がある」
「ただ、こっちは大型車がトラックなどがひっきりなしに来る」
避難先だけでなく、避難ルートも事前に決めました。このように1人ひとりの状況に合わせて作ったものを「個別避難計画」といいます。2021年改正された災害対策基本法で、作成が市町村の努力義務とされました。
作成した計画でスムーズに避難できるのか。12月4日の地域防災訓練では、寺田さんの母、牧田睦子さんの避難訓練が行われました。支援するのは、事前に決めた近所に住む人たち。睦子さんを車いすに乗せたまま外へ運び、近くの避難所に向かいました。
<牧田睦子さん(85)>
「みんな協力してくれるから、感心した」
<避難を支援した人>
「きょうは事前に準備をしていたので大丈夫だったが、いつ災害が起こるか分からないので、みんなに話はしてあるので、声掛けをしてやっていきたい」
富士市は国のモデル事業に選ばれ、個別避難計画の作成が進んでいます。それでも、支援が必要な人約2万2000人に対し、作成率は26.7%です。静岡県全体では8.2%に留まっています。
<牧田睦子さんのケアマネージャー>
「計画を立てて検証してみたが、変更点がいくつか気付きがあり、車いすを昇降するのも2人という計画だったが、男性3人必要だということが分かった」
実際に訓練をすることで気づくことも多くあります。個別避難計画の実効性を高めるには、本人や家族だけでなく、地域の人や福祉の専門職と連携した計画の作成・検証が欠かせません。しかし、牧田さんのように、うまく連携できたケースは富士市でも、まだ11例です。
<富士市役所 危機管理室 太田智久統括主幹>
「このモデル地区というものから市内全域に広げ、事業所の協力、地域の理解を広めながら、全域で作成を進めていきたい」
「誰ひとり取り残さない」防災の実現のため、地域一体となった取り組みが必要です。
注目の記事
4億3409万6000円(1等5口)出た!「ロト6」大島イータウンチャンスセンター “全国の1等9口のうち5口も” 富山・射水市

初代トヨタ・ソアラで「未体験ゾーン」へ、期間限定レンタカー始まる 80年代ハイソカーブーム牽引の名車、最上級グレード2800GT-Limitedの上質な走りを体感

“空き缶拾い”で生きる男性に密着 無断での持ち去りは50万円以下の罰金へ…名古屋市の「禁止」条例がことし4月に施行

立憲・公明が「新党結成」の衝撃 公明票の行方に自民閣僚経験者「気が気じゃない」【Nスタ解説】

「僕の野球人生を最後このチームで全うできればいい」楽天・前田健太投手に独占インタビュー

宿題ノートを目の前で破り捨てられ「何かがプツンと切れた」 日常的な暴力、暴言…父親の虐待から逃げた少年が外資系のホテリエになるまで 似た境遇の子に伝えたい「声を上げて」