■「とにかく知りたい」核心に迫る発見も…
「調べれば調べるほど深まる謎」を解き明かそうと、研究チームが向かったのは…

(新幹線の車内アナウンス)
「間もなく新横浜です」

横浜市にあるレンタルラボ。

最新鋭の「X線CT検査装置」が揃った、アジアではナンバー1。世界でもわずかだという施設です。

(加藤教授)
「すごいな…いままでの苦労が」

(CTのオペレーター)
「病院のCTなど、生きているものにX線をあてるものは、そんなに出力が上げられないので大分弱いんですよね」
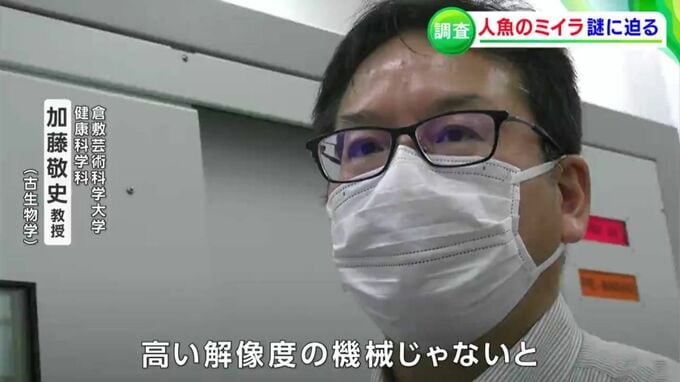
(倉敷芸術科学大学 加藤敬史教授)
「高い解像度の機械じゃないと、どうしても骨一つ一つを細かく見ることができなかったので。尾部骨格ですね。これは魚の分類に非常に役に立つ。それからひし形のウロコがありますので、そのひし形のウロコの細かい形態を確認したい」
いよいよ、検査の結果が画面上に映し出されます。

(加藤教授)
「うわ~、“まきびし”みたいだ。本当に“まきびし”みたい」

生物用のCT装置では、何となくしか分からなかった「腕のウロコの形」が、はっきり確認できます。
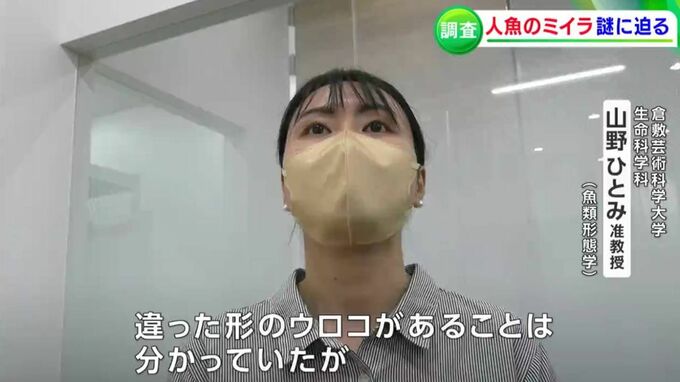
(倉敷芸術科学大学 山野ひとみ准教授)
「『違った形のウロコがある』ということは分かっていましたけども、より形がはっきり分かったということでですね。どういう違いがあるのか、はっきりとした情報をみなさんにお伝えできるかなと」
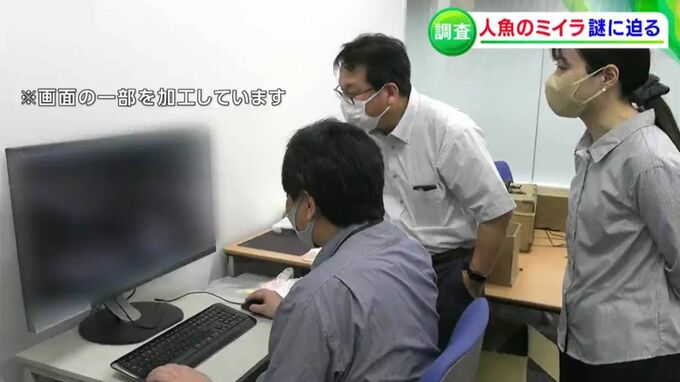
最終報告の日まで明かすことはできませんが。。。核心に迫る“ある部分”も確認できました。
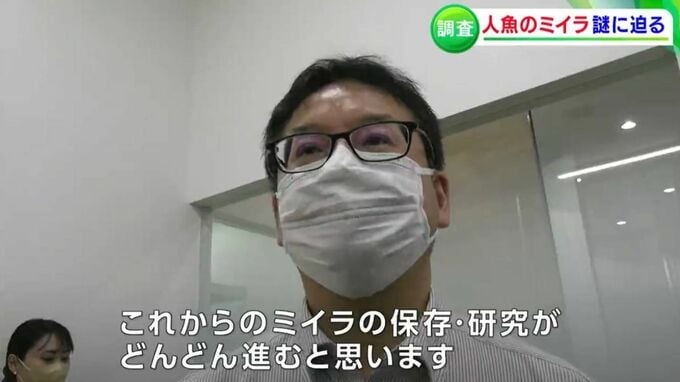
(倉敷芸術科学大学 加藤敬史教授)
「取得できたCTの画像を加工して、それぞれパーツごとに細かく切り分けながら見ていきます。これからのミイラの保存・研究がどんどん進むと思います」
■円珠院に帰ってきた「人魚のミイラ」 研究の最終報告は2023年1月に

(加藤教授)
「結構長旅だったんですけど…横浜まで…遠くまでミイラ様も初めて行かれたことだと思いますけど」


検査を終えて、長年所蔵されてきた浅口市鴨方町の円珠院に、ようやく帰ってきました。

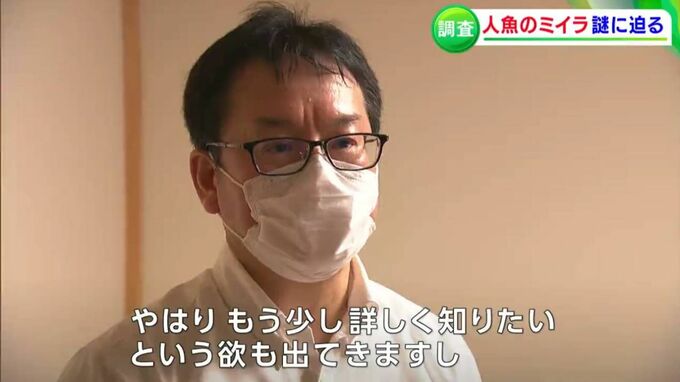
(倉敷芸術科学大学 加藤敬史教授)
「とにかく我々は『何だこれは』というのが一つありましたけれども、研究の過程で少しずつ色々なことが分かってきました。やはり『もう少し詳しく知りたい』という欲も出てきますし、それが結果的には保存の役にも立つ」
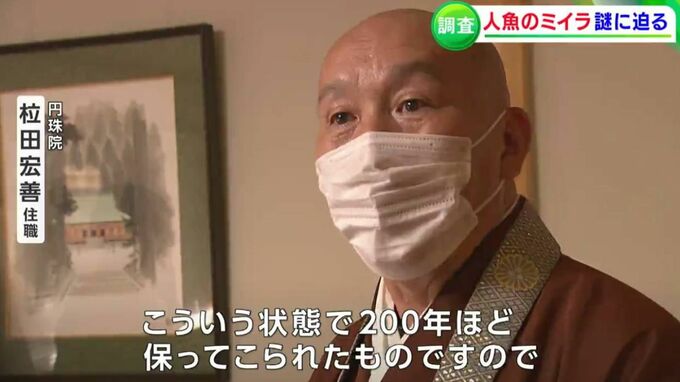
(円珠院 柆田宏善住職)
「私とすれば、それが何者であろうと同じかなと思うので、こういう状態で200年ほど保ってこられたものですので、それ以上のものをこれから先も100年、200年と守っていくのが一番かなと思っていますので」


科学的な分析に終わるだけでなく、『古くから民間信仰の対象だった人魚のミイラの本質にも迫ろう』というプロジェクトです。来年1月中の最終報告を予定しています。

















