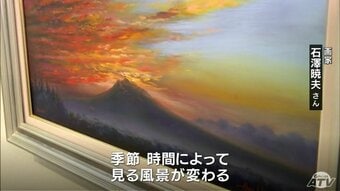犯罪が起きやすい危険な場所を把握するための授業が、青森県弘前市で行われました。小学生たちは、警察官とともに実際に通学路となっている学校周辺の道路に繰り出して安全に登下校をするためのルートを学びました。
弘前市立西小学校で行われた「地域安全マップづくり教室」は、県警察本部が幼少期から危機管理能力を育んでもらおうと毎年、小学生を対象に行っています。
はじめに県警の木村靖弘 警部補が、参加した小学5年生の児童27人に対して犯罪を予防するためには人の見た目ではなく「入りやすく見えにくい」犯罪が起きやすい場所を把握することが重要だと伝えました。
その後、子どもたちはグループに分かれて実際に学校周辺の「入りやすく見えにくい」場所を調査。周りが高い木で覆われている道路などの危険な場所や、子どもが助けを求められる『110番の家』の位置などを確認しました。
参加した児童は
「子どもだけでいったらダメなところなどが分かってよかった」
「学校の周りで危険な場所を知ることができたので、そこに夜はできるだけ1人で行かないようにしたい」
県警察本部によりますと、子どもや女性などへの「声掛け」や「つきまとい」など犯罪につながる可能性がある脅威事犯は、9月末時点で314件となっています。
なかでも下校の際の声掛けが多くなっていて、警察は日頃から危険な場所を意識して防犯に努めてほしいとしています。