世界有数のウミガメの産卵地屋久島で、外来種のタヌキによる子ガメへの食害が確認され、環境省などが調査しています。

こちらは今年8月に屋久島北西部の永田で撮影された映像です。ふ化して間もない子ガメをタヌキがくわえています。別の映像では、子ガメがいると思われる砂浜を掘っている様子が分かります。
撮影したのは、ウミガメの資料展示などを行う「屋久島うみがめ館」です。

雑食のタヌキはもともと屋久島にはいない国内外来種で、30年ほど前に人の手で持ち込まれたとみられています。子ガメや卵を狙うのはノネコやカラスもいますが、近年タヌキの被害が増えているといいます。
(屋久島うみがめ館 上田博文代表)
「かなりショッキングな映像」
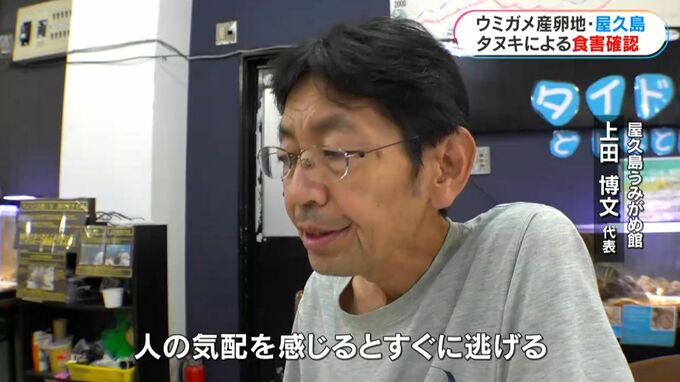
Q.調査でまわっていて遭遇したことは
「タヌキは非常に臆病、人の気配を感じるとすぐに逃げる」
永田浜には、絶滅が危惧されているアカウミガメとアオウミガメが春から夏にかけて上陸し、およそ1700回の産卵が確認されています。

一方タヌキは、島全体に生息していて屋久島町は年間300匹から500匹を捕獲しています。
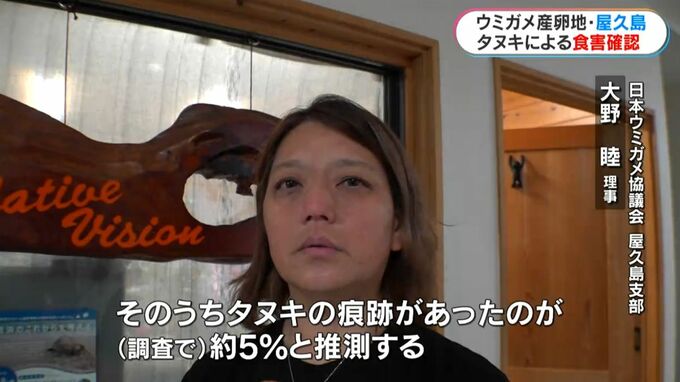
(日本ウミガメ協議会・屋久島支部 大野睦理事)「去年、永田浜でウミガメの孵化脱出が900巣確認された。(調査から)そのうちタヌキの痕跡があったのが、(調査で)約5%と推測する。関係機関と協議しながら(対策に)取り組んで行きたい」
環境省もタヌキの詳しい生態や生息数などは十分に把握できていません。
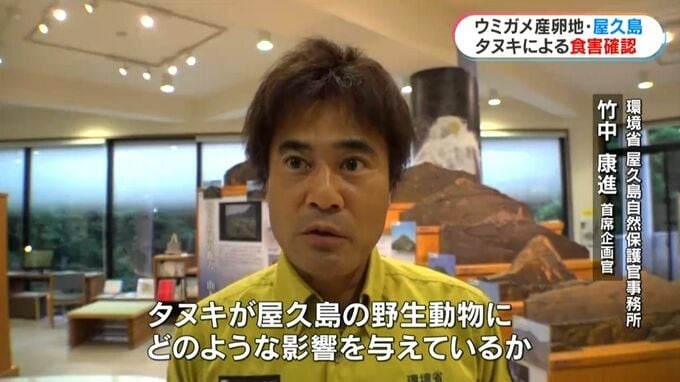
(環境省・屋久島自然保護官事務所 竹中康進首席企画官)「世界遺産エリアも含めて、タヌキが屋久島の野生動物にどのような影響を与えているか、まだ分かっていない状況」

野生動物による子ガメや卵の捕食が、生態系に与える影響がわかるのは数十年後とみられ、環境省や屋久島町、保護団体は産卵地の監視や被害の調査などを進めています。














