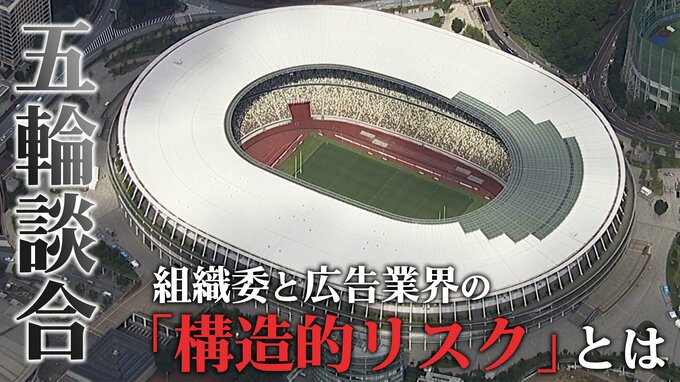東京オリンピック・パラリンピックを巡る捜査は、高橋治之元理事を中心とした「汚職」から、五輪の運営資金を巡る「談合」に、その舞台を移した。東京地検特捜部と公正取引委員会は、五輪のテスト大会の業務の入札で談合を行った疑いで、新たに電通と博報堂の広告2強を含む8社の強制捜査に乗り出した。スポーツの祭典の裏で何が起こっていたのか。取材から浮かび上がったのは、五輪という巨大イベントを運営するために作られた、組織委員会が抱えていた「構造的リスク」だった。“官と民”が入り交じった組織で疑惑は生まれた。
■電通と組織委員会が談合を主導か
2018年5~8月、組織委員会は、東京五輪の本大会前に行う「テスト大会」について、26の会場ごとに計画立案業務の入札を実施した。しかしほとんどの入札で応札した社は1社にとどまり、競争が無いまま受注業者が決まることになった。26の業務は、電通や博報堂など広告会社とイベント会社の計9社・1団体が分け合い、結果、契約額の総額は5億円余に達した。

問題の入札では「組織委員会の幹部」「電通から組織委員会に出向した職員」「電通の五輪担当者」の3者が主導し、談合が行われたとみられている。関係者によると、電通の担当者が各社から意向を聞き取り、調整した上で、受注予定業者の一覧表を作成。一覧表は組織委員会の幹部とも共有されていたとされる。実際、落札した業者は、ほぼこの一覧表の通りだったという。
受注した企業の幹部
「電通より安い価格で入れちゃ(入札しては)ダメなんだ」
「電通と話して、いくつか会場(業務)を取れることになった」
広告業界の周辺関係者は、「業務を受注した企業の幹部は、調整の実態をあけすけに語っていた」と話した。そこに違法性の認識は感じられなかったという。
■組織委元幹部が語った「構造的リスク」
なぜ疑惑を生むような調整が行われたのか。組織委員会の元幹部はこう振り返る。
組織委員会 元幹部
「組織委員会が構造として談合を生み出すリスクを内包していたのは事実だ」
業務を発注する側の組織委員会には、受注する側である広告会社やイベント会社の社員が数多く出向していた。都庁などからの出向者らに、大規模イベントを運営した経験などほとんど無かった。五輪運営に関するほぼすべての業務で、広告会社やイベント会社から出向してきた“百戦錬磨”の職員に頼るところが大きかったという。組織委員会の元幹部は「発注側に彼らがいることで談合の危険はあったが、当時はとにかく専門家が必要という感覚だった」と話した。
さらに当時、組織委員会が抱えていた“懸念”も、談合を後押しした可能性がある。
組織委員会 別の元幹部
「人気のない競技をどうやってやってもらおうかと悩んでいた」
「万が一、引き受ける業者がいなかったらヤバいという懸念が組織委員会にあった」
大会準備の期間中、組織委員会は、常にIOC(国際オリンピック委員会)からのプレッシャーにさらされていた。IOCは大会準備の進捗状況について頻繁に報告を求めており、マニュアルに沿って「何か月前には、この段階まで終わっていなければならない」と指定されていた。利益が見込めないという理由で業務の入札が不調に終われば、当然スケジュールは遅れる。受注企業の関係者は「組織委員会も電通も『五輪は日本を世界にアピールする場だから、色々な企業が関わり、みんなでやっていく必要がある』と言っていた」と述懐する。
しかしある捜査関係者は、こう切り捨てる。
捜査関係者
「特殊な事情があるならば、条件を整備して随意契約にすればいい。だれもが入札に参加できるのが、自由市場だ。入札で調整してはだめだ」