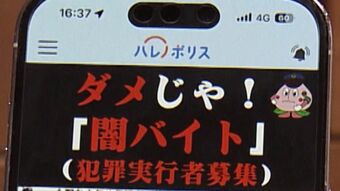ハンセン病療養所の入所者に法曹界はどう対応したのか
(井上雅雄弁護士)
「この講演では、『ハンセン病と法曹界』ということで、法律家たちがどう関与してたのかという話をしようということなんですけども、法律を作るのも一応多少関与していたのかもしれませんが『らい予防法』という法律が、1953年に制定されています。
本来であれば、この段階、あるいは、これよりもっと前の段階で、重大な人権侵害の問題のある法律であり、かつハンセン病患者への差別偏見が発生している状況だったので、法曹界として、本来は、弁護士が、法律を作る段階からストップをかけなきゃいけなかったんだろうと思うんですけれども、あまりというか全く、私の知る限りでは動いてなかったと思います。
この『らい予防法』が制定される当時、ハンセン病療養所の入所者でつくる協議会がすごく、国に対して反対運動をしておられまして、『らい予防法』が制定された後も、少しでも療養所内で暮らしやすくなるような闘争を継続されていました。
それに対しても、弁護士が誰かサポートしていたっていう話は聞いたことがないです」
菊池事件とは

「ハンセン病療養所にいる人たちが、ある一定の時期からは、体内かららい菌が出なくなった場合、退所して地域で暮らすということになっている。そういう方々も多くいます。
あるいは、療養所から逃げた人が過去にもいますけど、そうした人が関係して、療養所の外で事件が起こることがありました。
そうした事件の1つの大きな事件として菊池事件という事件が、1951年と52年にありました」
(1951年、熊本県北部の元役場職員男性の自宅に爆発物が投げ込まれる事件があり、ハンセン病患者の男性が逮捕されました。患者の男性は、菊池恵楓園の中で開かれた熊本地裁の出張裁判=特別法廷で懲役10年の判決を受けます。患者の男性は、この判決に対して控訴しますが、その控訴審中、留置場から逃走し指名手配されました。その3週間後、爆発物を投げ込まれた元役場職員が山中で殺されているのが見つかりました。その後、山中の小屋に隠れていた患者の男性が銃で撃たれ逮捕されました)
「この事件の被告は、療養所内に作られた法廷で死刑判決を受けます。本当に、裁判といえないような裁判で判決がなされました。通常の法廷ではなかったのです。
控訴し、上告しても退けられ、刑は確定します。
再審請求がずっと続いてたんですけれども3回目の再審が却下されたその翌日に死刑が執行されるということが起こってしまいました」