◆「完全給食」に移行する自治体も
一方で、選択制から全員制の完全給食に移行する自治体もあります。
RKB三浦良介「太宰府市は、来年度から完全給食に移行することを決めました」
太宰府市は、現在、民間の給食事業者の選定を進めていて、来年度のできるだけ早い時期から全員制の完全給食を始める方針です。
太宰府市 楠田大蔵市長「弁当の準備なども大変だという声もお聞きしていました。また太宰府市としても、かつていろいろな混乱の原因になってきましたので、私自身が市長としての使命として実現に踏み出そうという思いに至りました」

また、2017年に中学校で「給食選択制度」を採用した直方市も、今年度の2学期から全員への完全給食に切り替えています。
◆「子供の貧困」と「給食の役割」
食の現代史が専門で給食の歴史に関する著書もある京都大学の藤原辰史准教授に聞きました。
京都大学 藤原辰史准教授「給食は元々、どんなに経済的に苦しい状況にある子供たちでも、みんな同じものを食べることができて経済的な格差を感じなくてもいいように設計されたもの。物価高、そして子供の貧困が非常に問題視されているこの時代において、とても大きな役割を果たしていくと思います」
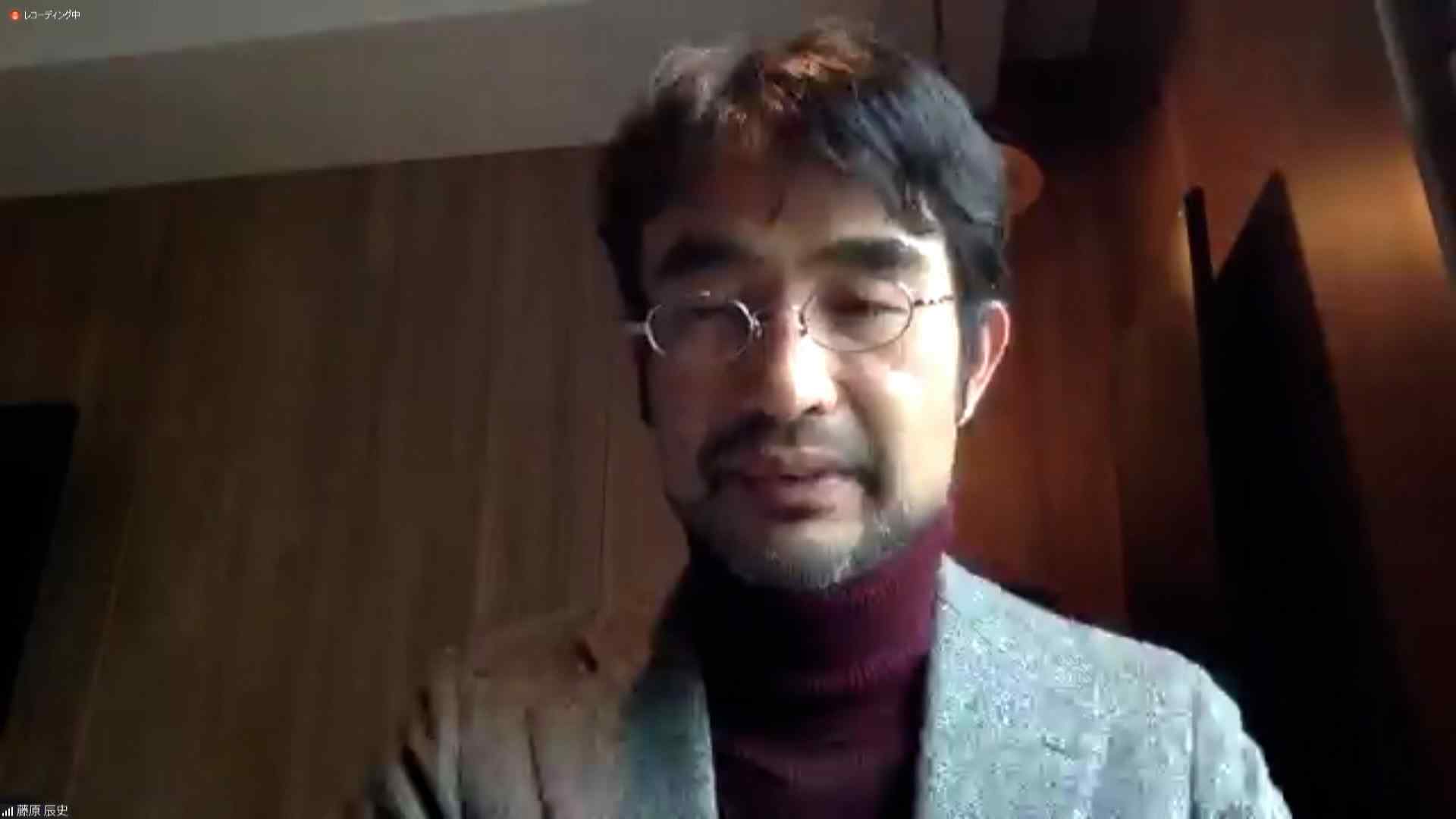
【ポイント整理】
文部科学省の定義では、給食の提供スタイルは3つに分けられます。主食とおかず、牛乳が提供される「完全給食」、主食は持参し、おかずと牛乳が提供される「補食給食」、そして牛乳のみを提供する「ミルク給食」です。これは、提供する数は関係ありません。一部の生徒にでも提供していれば取り入れていると判断されます。
大野城市の教育委員会は、現在も選択制度を使って希望する生徒に主食とおかず、牛乳を提供しているから「完全給食」を取り入れていると主張しています。一方で、市民団体が求めているのは、生徒全員に「完全給食」を提供すること、ほかの多くの自治体と同じように生徒全員に同じ食事を提供することです。法律の解釈ではなく、生徒や保護者が何を求めているのか、もう少し本質を見るべきではないでしょうか。














