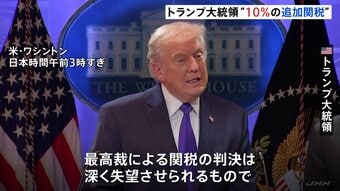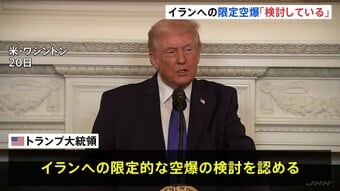映像を加工し自在に演出

炎、電流、破壊など、異能力に応じてさまざまなVFX表現が求められる本作。それぞれに異なるアプローチが必要とされる。
「物を破壊したり、炎を出したり、電流を走らせたりと、能力ごとに処理が違ってきます。炎はパソコン上でシミュレーションを行って空間の揺らぎを演出しますし、破壊するシーンでは現実にあるものとそっくりなCGを作って、それを壊すという手法を取っています。電流の移動などは、主に実写映像に2Dの要素を加えて作るなど、2D上で処理することもあります」。
一方で、撮影現場で臨機応変な対応が求められるケースも少なくない。撮影当日、ジウが異能力を発揮するという表現が急遽追加されることがあったという。
段どりの最中にいきなり、ここで異能力の表現を足せないかという話になったんです。僕としてはなんとかやりたいと思いましたが、そもそもどういう能力なのかがきちんと決まらないまま撮影をすることになってしまいました。完成を想定しないで撮影したものに後から合わせて加工するのは大変ですね」と朝倉氏。

こうした撮影後の加工にこそ用いられるのが、VFXだ。VFXでは、実際に撮影した映像に対して、コンピュータを用いて加工を施せるため、ワイヤーアクションで浮かんだ人物の支えを取り除いたり、建物の映像に火や煙を加えたりするなど、さまざまな演出効果を後から加えることができる。
VFXとは撮影された映像に処理を加える工程のこと。その中にはコンピュータ上でゼロから物を作り出すCG技術や、それらのCGや撮影された素材を重ね合わせて一つの映像にするコンポジットワーク(いわゆる合成作業)が含まれている。
こうした特性上、VFXは現場で起きたイレギュラーな動きにも柔軟に対応できる一方で、完成形を想定しづらい場合は、調整の難易度も一気に上がってしまうという。朝倉氏が「大変」と漏らしたように、その柔軟性は、裏を返せば高度な技術と判断力が求められるということも意味する。