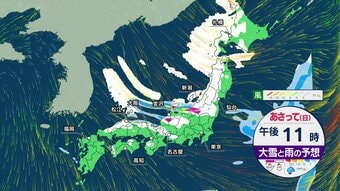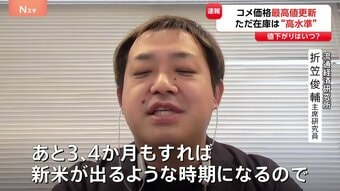「楽しいからやる」──子どもの本能を起点にする

金融知識や防災訓練のエンタメ・ゲーム化などを手掛けるSEGA XDの伊藤真人COOは、「教育とエンタメを切り分けること自体が大人の都合」だと語る。
「子どもは“楽しいからやる”。その結果、学びが生まれる。今は、“エンタメが教育につながる”という流れが、受け入れられる時代になってきている」
この発想の転換が、エデュテインメントの根幹にある。かつての“教育を楽しくする”のではなく、“楽しいことが結果的に学びになっている”という従来とは逆のプロセス構造こそが理想形だ。
子どもにとっては「遊び」、でも親からみたら「学び」になっている納得感
知育アプリ「シンクシンク」や「ワンダーボックス」を開発するワンダーファイCEO・中村友香さんは、“子どもにとっては完全に遊び”でありながら、“親にとっては教育的に意味があるもの”としてエデュテインメントが成立しはじめている時代だと強調する。
「子どもたちにとっても完全に遊びなんです。でも、保護者から見たらそれが教育的に意味がある。遊びと学びって、もはや別物じゃないと感じていると思います」
そしてこの「親の納得感」こそが、エデュテインメントにおけるビジネスモデルの強みだ。ゲーム課金には抵抗がある親も、「教育的に価値がある」と感じれば、安心してお金を出せる。単なる子ども向けコンテンツではなく、“家庭内の知的消費”となる新たな商品ジャンルとも言える。