水難事故には冷静沈着を…助ける側としての意識も
高柳キャスター:
皆さんに覚えてほしいのは「ういてまて」の5文字です。
呼吸を確保するときの姿勢として、3つのポイントがあります。
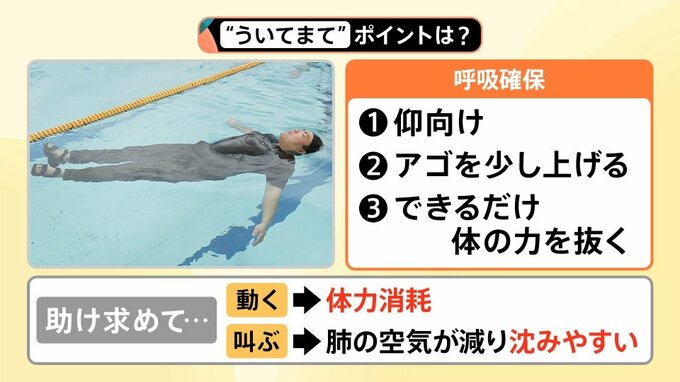
(1)仰向けになる
(2)アゴを少し上げる
(3)できるだけ体の力を抜く
体が水面に入っているとき、外に出ていられるのは(体の)約2%ほどといわれていますので、その2%を口元にすることが一番大事になってきます。
どうしても助けを求めたくなってしまいますが、動くと体力を消耗しますし、叫んでも肺の空気が減って沈みやすいという、負の連鎖に陥ってしまいます。
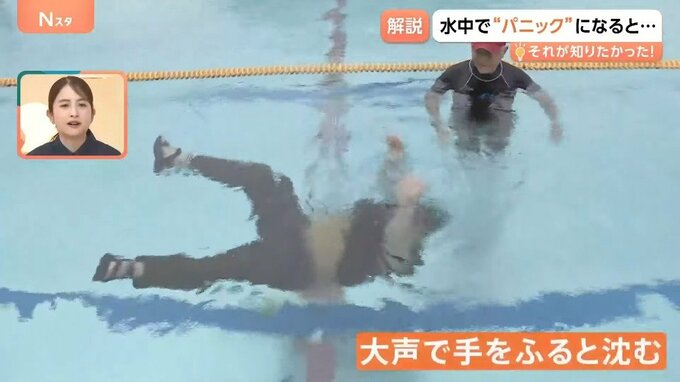
秋本記者:
普通に浮いている状態で「助けて」と声を出し、手を振ってしまうと、本当に一瞬で沈んでしまいます。
日比キャスター:
体のバランスが崩れてしまうということでしょうか。
秋本記者:
そういうことです。空気が抜け、沈んでしまいます。
高柳キャスター:
緊張状態でいかに冷静になって、叫ばず、動かずにいられるかが大事になってくるということです。
溺れている人やパニックになっている人を見かけた場合、我々はどう対処すればいいのでしょうか。

【流されている人を見かけたら】
▼飛び込んで助けに行かない
▼すぐに消防へ連絡(119番)
▼「ういてまて」大声で叫ぶ
▼ペットボトルなど浮くものを投げる
(水難学会 斎藤理事によると)
秋本記者:
声をかけられると安心感があります。
常に「見ている」ということを流されている方にもわかってもらい、ちゃんと浮いてもらうという意識が大事だと思います。
日比キャスター:
「助けたい」と思って水に入り、共に事故に巻き込まれるというケースも過去にありました。
まず落ち着いて「ういてまて」ですね。
南波キャスター:
ウエストポーチのような、かさばらないライフジャケットもありますので、岸際で遊ぶときも、そういったものを活用してみてもいいかもしれません。
==========
<プロフィール>
秋本壯樹
TBS報道局社会部 警視庁・東京消防庁担当
「海の日」は子どもとプールに行く予定














