7月21日は「海の日」ですが、早くも水難事故が数多く発生しています。もし、海や川で流されそうになった場合、どう対処すればいいのでしょうか。
水難事故には「ういてまて」…あなたはこの言葉を実践できますか?
高柳光希キャスター:
18日、関東を中心に梅雨明けとなりました。本格的な暑さが広がり、夏が始まります。
そんななか、21日の海の日を前に、水難事故が多く発生しています。

2024年の水難事故の発生件数は1535件で、過去10年で最多となっています。(警察庁資料より)。
なぜ水難事故は増加しているのでしょうか。

水難学会の斎藤秀俊理事によると、理由の一つは「猛暑」です。連日の暑さのなかで、水のレジャーに触れる機会が増えていることが挙げられます。
そして、ゲリラ雷雨などの「天気の急変」も一つの要因となっています。
さらに挙げられるのは「水に触れる機会の減少」です。近年、学校でプールの授業が減っていることも大きな要因です。
TBS報道局社会部 秋本壯樹 記者:
水難学会の斎藤理事によると、「猛暑の影響でプールの授業の中止が相次ぎ、事前の安全対策を受けないまま、水の中に入ってしまうことが原因に挙げられる」といいます。
高柳キャスター:
実際に溺れてしまったときやパニックになったとき、どんなことを意識すればいいのでしょうか。
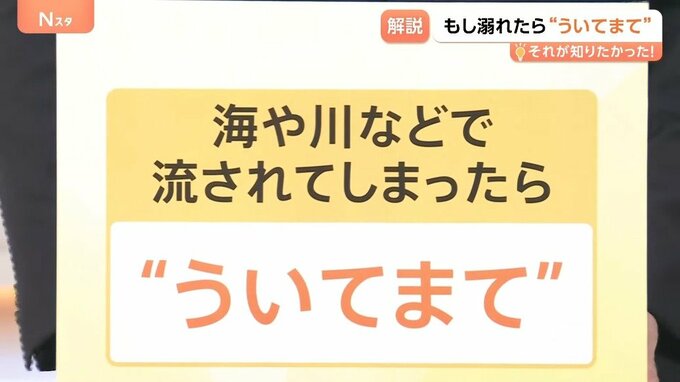
秋本記者:
斎藤理事は、海や川などで流されてしまったら「ういてまて」と呼びかけています。
焦らずに、正しく浮いた状態で救助を待つことが大事なようです。救助が来るまで、自ら呼吸を確保することが生還への一番の近道になるとのことでした。
「ういてまて」とは実際にどういうことなのか、私自身の体験をもってお伝えしたいと思います。














