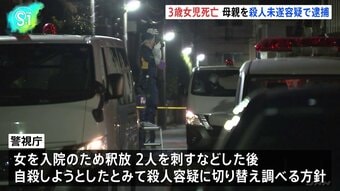◼︎「人間の本性は変わらない」アフリカにある普遍性
ーー確かに『ムクウェゲ』をみていると、場所の違いを忘れてしまう感覚がありました。描かれている性暴力の被害は凄まじいのですが、背景に政治的、経済的な意味合いなどがあることが示されます。これまで私は性暴力を「性欲を満たすもの」としてしかとらえていなかったのですが、もっと根深い構造の可能性を知り、日本にもその構造は存在すると自分ごととしてみました。見る方によっていろんなとらえ方をしてもらえるように制作しました。おっしゃるように「性暴力」はアフリカの人たちが特別なわけではなくて、日本でも同じことが起きていて、例えば日本の家父長制の問題とつながるかもしれません。女性の権利に興味がある人はそういうところに目がいくし、国際政治に興味がある人は、何でアフリカの戦争が終わらないのかというところに関心がいくかもしれません。アフリカと日本で、場所は違っても“人間の本性”みたいなものは変わらないと思います。このことは、加害者側である元兵士たちについてもいえると思っています。
ーー数百人のレイプに関与した加害者である元兵士たちは、顔を出して証言していますね。そして、悪びれるわけでもなく、性暴力を加えるに至った自分たちの立場を話します。聞きながら、加害者なのか、被害者なのか、戸惑いました。
取材に意外とあっさり応じてくれて、私も驚きました。日本の感覚からすると「申し訳ございません」という言葉が出てくるのを期待しますよね。でも、彼らは「自分から進んでではなく、命令されてしょうがなくやったんです」と話をします。つまり、彼らは「加害者」でもあり、「被害者」でもあるんです。

◼︎「“偽善”であると意識するから、一生懸命伝える」
ーーなぜそこまで“つながり”を重視するのでしょうか?私たちの仕事に対して、責任を感じているからです。実は私はこの仕事は“偽善”だと思っているんです。取材するにあたって、「大変ですね」とか「日本の人に伝えなきゃいけないんですよ」とかもっともらしいことをいっています。でも、私は被害者たちに替わってあげられるわけでもないし、ずっとアフリカに住むわけでもありません。ちょっとだけアフリカに行って、何かわかったようにして取材して、寄り添ってます、みたいにして。でも、しれっと安全で快適な日本に戻ってきて、今日ご飯何食べようかなとか、家族と喧嘩しちゃって嫌だなとか、明日何着て行こうかとか、自分の身の回りのことに追われる平和な日常を送るわけです。それって“偽善”じゃないかなって。
だから自分がしている仕事は“偽善”だと、常に自分が忘れないってことが私の職業倫理です。だからといって、平和な日常を否定するつもりはありません。日々の暮らしは大事です。24時間世界のことばかり考えて生きていくことはできない。自分の仕事は偽善であるからこそ、自分のできる限りのことをしなくてはならないと思っているんです。
ーー具体的にはどういうことでしょうか?
例えば、映画では性暴力の被害にあった女性たちが自分たちの経験を話してくれました。思い出したくないことを聞くというのは正直残酷な仕事だと思いました。しかも、見ず知らずの私に話してくれたんです。

私は彼女たちを苦しみから救ってあげられるわけではありませんし、日本に戻って24時間彼女たちのことを考え続けられるわけでもありません。でも勇気をもって一生懸命話してくれたのだから、私も一生懸命日本の人たちに伝えなきゃいけないと思うんです。裏を返せば、私には伝えることしかできない。そしてそれが自分の責任だと感じています。
ではどう伝えるかというと、遠い国のことだからどうでもいい、知らない人だから関係ない、ではなくて、彼女たちは私たちの生活とつながっていて、実は私たちも彼女たちの被害に加担しているかもしれない、アフリカで起きていることの構造自体は日本にもあるかもしれないと想像するきっかけとなる伝え方をしなくてはいけないと思うのです。