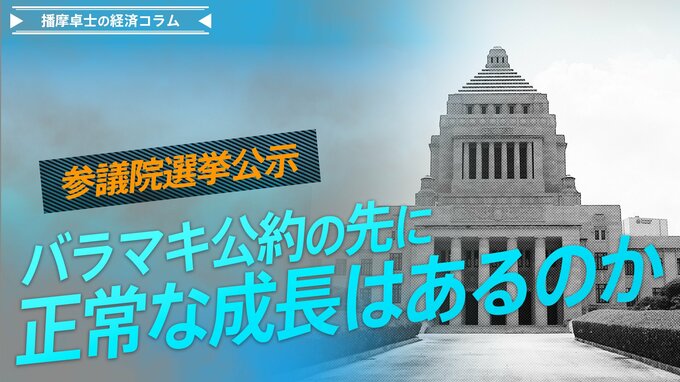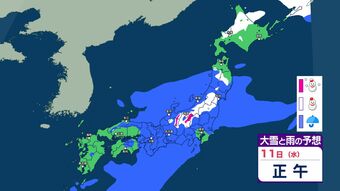参議院選挙が公示され、20日の投票日に向けて選挙戦が本格化しています。最大の争点は「物価高対策」で、給付金か消費税減税か、をめぐって、与野党が互いにバラマキと批判しています。国民全員にお金を分配するという意味では大して変わりはなく、「どっちもバラマキ」というのが、本当のところでしょう。
現金給付も消費税減税もバラマキ
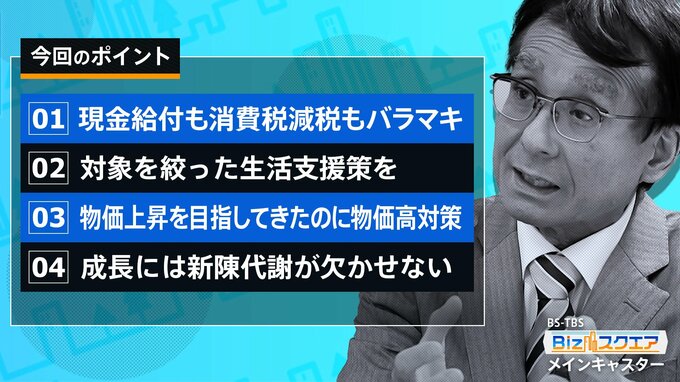
「国民全員に2万円」という自民と公明の案、石破総理は、子供や住民税非課税世帯に2万円加算する点を取り上げて「メリハリはあり、バラマキではない」と強調しています。しかし、所得の高い人も含めて国民全員に2万円配るわけですから、これをバラマキと呼ばないのなら、何がバラマキなのかと、問い返したくなります。
一方、野党側は、立憲と維新が食料品に限って消費税を時限的にゼロに、国民は消費税全体を5%に、共産、れいわ、参政は消費税の廃止を、それぞれ掲げています。食料品であれ、一般物品であれ、世の中に消費をしない人はまずいないので、こちらもすべての人が減税対象です。まして消費金額の多い「お金持ち」になるほど減税額が大きくなるのですから、こちらもバラマキに違いないでしょう。
消費税のあり方を議論することは意義のあることですが、短期的な景気対策や生活支援策としてではなく、長期的な税制のあり方として議論されるべきではないでしょうか。
対象を絞った生活支援策を
まず考えるべきことは、今の経済状況が国民全員にお金を配らなければならないほど、危機的なのかということです。大恐慌やコロナ禍のように、あらゆる経済活動が止まり、大多数の人が失業のリスクにさらされた際には、全員にお金を配る政策には意味があります。それは、国にしかできないことです。
しかし、2年連続で30年ぶりの高い賃上げが実現し、人手不足が深刻で、マクロ的にも需給ギャップがほぼ解消した現状が、それに当てはまるとは思えません。
問題なのは物価高が予想外に高く、長く続き、賃金などの収入がそれに追いつかない人々が多数いるという現実です。要は、そうした方々への生活支援が必要なのです。生活支援が必要ない「お金持ち」や、もっと言えば、賃上げが物価高に追いついている人には、何も国がお金を配る必要などないはずです。
政治に求められるのは、そうした「本当に困っている人」を特定して支援の方法を整えることです。もちろん、「本当に困っている人」を特定するのは困難です。例えば、賃金が物価高に追いついている人を特定するなんてことは大変でしょう。それでも、年収はもちろんのこと、それに扶養家族の数などを加味して、できるだけ絞り込んで支援を行うことが大切なのではないでしょうか。
国の財政がこれだけ悪化しているのに、主要政党のすべてが全員に給付や減税をすることを公約に掲げ、逆に、全員支援がおかしいという主要政党が一つもないというのは、不思議なことです。