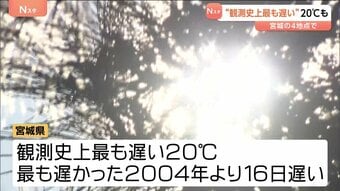セブン&アイ・ホールディングスは11月11日、傘下の百貨店のそごう・西武をアメリカの投資ファンド・フォートレスに売却することを正式に決定しました。フォートレスは家電量販店大手のヨドバシカメラと連携しており、旗艦店にヨドバシカメラが出店するなどして、そごう・西武の再建を進めることになります。一方、セブン&アイは、主力のコンビニ事業や海外展開などに経営資源を集中させ、一層の成長を目指します。
バブル崩壊後に経営危機に陥った、そごうと西武百貨店は、2003年にミレニアムリテイリングとして経営統合し、2006年にセブン&アイの傘下に入りました。そこにはセブン&アイの経営者である鈴木敏文氏の、百貨店も含めた総合小売業への強い思いがありました。
ダイエーの創業者・中内功氏がそうであったのと同様に、スーパー業界には、いつかは百貨店を持ちたいという気持ちが根強くあったのでしょう。百貨店こそが、消費の“華”であった時代です。
しかし、流通小売りの覇者であるセブン&アイをもってしても、デフレ時代の百貨店再興の道は険しく、全国に28あったそごう・西武の店舗が今や10店舗になるなど、縮小均衡から抜け出せず、逆にグループ経営の重荷になっていました。
江戸天保年間に大阪で創業したそごうは、積極的な多店舗展開で一時、業界1位の売上高を誇った存在ですし、西武百貨店は、眩しいほどの消費文化の花が開いた1980年代に、海外ブランドや美術館なども導入し、ファッション・文化の発信地として一世を風靡しました。
その80年代に20代の若者であった私にとって、西武百貨店は「背伸びしてでも買いたい」と思わせてくれた場所でした。いずれも「消費を楽しむ」ということを、一部の富裕層から、いわば「普通の人々」の手に届くものにした存在でした。「中流」による「大衆文化」を体現した舞台だったとも言えるでしょう。
百貨店業界は、長いデフレ時代に消費不振の直面し、業界再編も経るなど厳しい時代を経験しました。その背景には、国民の「中流」意識の崩壊や、新たなタイプの量販店の進出といった構造変化もありました。百貨店は、今は再び、富裕層をターゲットにした高級品に焦点を当てると共に、インバウンドに活路を見出そうとしています。
今後、そごう・西武を買収したアメリカの投資ファンドがどのような再建策を描くのかは、まだ分かりませんが、投資ファンドに、日本の百貨店を再興する「魔法」があるとは思えませんし、ヨドバシカメラが入っただけで百貨店自体が再生されるわけもありません。厳しい見方をすれば、そごう・西武はいずれ「駅ビル」化するように思えますし、新たなオーナーである投資ファンドは、その不動産価値を高めることに、むしろ関心があるのかもしれません。
百貨店の一時代を刻んだ、そごう・西武の売却は、百貨店という業態が日本でどのように生き残れるかを、改めて問いかけているように思います。
播摩 卓士(BS-TBS「Bizスクエア」メインキャスター)
注目の記事
新幹線や特急列車で荷物を置くため「1人で2座席分購入」はアリ?ナシ? JRの見解は… 年末年始の帰省ラッシュ・Uターンラッシュ 電車内での“荷物マナー”

急増するパキスタン人に相次ぐ攻撃…ロケット花火やバット 「嘘だと思われる」直撃したユーチューバーを取材 見えた目的と誤情報 地域社会での共生に深い影

1匹見かけたら、3年後には2万匹に…爆発的繁殖力「ニュウハクシミ」の生態 文化財をむしばむ小さな脅威

「ごめんね」自らの手でロープをかけ…アルコール性認知症の息子(当時55)に絶望し 殺人の罪に問われた母親(80)が法廷で語ったこととは

「ただただ怖くて…家にいられない…」地震で“恐怖の場”となってしまった自宅 壁は大きく裂け鉄骨は曲がり… 今も続く不安を抱えながらの生活【最大震度6強 青森県東方沖地震 被災地のリアル①・前編】

「米はあるのに、なぜ高い?」業者の倉庫に眠る新米 品薄への恐怖が招いた“集荷競争”が「高止まり続く要因に」