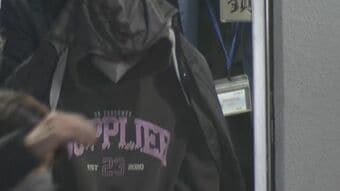4人の山師 伝え継ぐ技
今は4人しかいない山師。かつての山師の姿を、次の世代に伝えたいと考えていた實さんの遺志を竜二さんは引き継いだ。

山師 本田竜二さん
「日本全国探しても、この仕事をしているのは自分たちだけ。他にする人たちが出てくればいいが、出てこない以上は(やるしかない)」
今は切り株やすでに倒れた屋久杉を切り出している。大木ともなればチェーンソーでもなかなか切れず、使い方にも技がいる。
本田竜二さん
「中から切るのじゃなかったのか」
切り方を間違えると、木の重みでチェーンソーが挟まれ抜けなくなる。切った幹が倒れてくれば、命に係わる。どの手順で、どこを切るのか、山師としての力量が問われる。
本田竜二さん
「軽い音から重い音に変わっただろう。途中音が抜けて軽くなった。いま(刃が木に)入っている」
「いまはバー(刃)全体に木が乗っている」

屋久杉は、幹の中心が腐り、空洞になっていることがある。空洞に刃が入ると、その瞬間、音の響きが変わるという。経験が少ない若手には判断が難しい。
本田竜二さん
「ぼちぼち、ぼちぼち、少しずつ。いっぺんには無理でしょうから。経験する量が違うから、僕らの時代と比べると」
この日は、一番弟子の山師・松元さんと森に入った。竜二さんは、山師の森を感じてほしかった。生い茂った木々に行く手を阻まれながら登ること1時間...
本田竜二さん
「それだよ、大きさ全然違うでしょう」
山師 松元文明さん
「(3番目に大きい)『紀元杉』でどれくらい?」
本田竜二さん
「3000年ぐらいじゃないか」
松元文明さん
「一緒ぐらいと言えば一緒ぐらいかもね」

カメラが初めてその木を記録した。林野庁のリストでは、3番目の大きさに相当する巨木だった。
本田竜二さん
「(Q.作業する中で出会った?)そうです。林業関係者でも知っているのは一部」

屋久島の山に降る雨の量は、年間約1万ミリ。日本の平均の6倍もの雨だ。幹や枝は島特有の風雨にさらされる。細く長い屋久島の登山道。その外には、雨によって育まれた植物が生きる世界が広がっている。
森の奥に入ると、木々が行く手を阻む。また巨木が現れた。竜二さんによると、樹齢2000年を優に超える木だという。

本田竜二さん
「まんまるだから(幹周り)14~15m。木材がやっぱり豊富だった」
屋久島で2番目の巨木に匹敵する大きさだ。
多くの屋久杉を見てきた父・實さんだったが、切れなかった木があった。

本田實さん(当時83)
「普通の大きい木、一本立ちの木は何も感じないけど、2本同じところに立って上の方で絡み合っている木がある。そんな木は(切るのは)嫌だった。(Q.なぜ嫌だった?)神が宿る木という言い伝えがある」
山師たちの間で、この話は密かに語り継がれてきたという。竜二さんとともに再び森に入った。