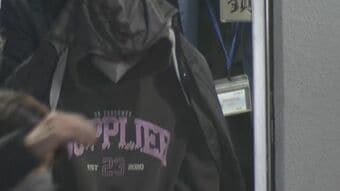切らなかった巨木 山師の思い

取材班は山岳ガイドらと山に入った。そこには見たことのない巨木が立っていた。木の上部は折れ、巨木の命はすでに尽きていた。しかし、幹に着生した植物たちが巨木を大地として葉を広げていた。それは、まるでひとつの「森」のようだった。

取材班
「こぶはここにあるし、これだけで1mぐらいある」
山岳ガイドが幹の周りをテープで測る。ガイドが両手を広げた長さは175センチ。

山岳ガイド 田平拓也さん
「16m…『縄文杉』と変わらない」
その巨大さに山師は、この木を残すことにしたという。
取材班
「よく山師の人は切らなかったですね」
田平拓也さん
「そうですね、本当にありがたいです」
なぜ山師は切らなかったのか。その背景は…。

高度経済成長期、住宅用の木材需要が高まると、国の方針で屋久島の森は大伐採が進んだ。樹齢1000年を超える屋久杉も伐採の対象となり、大量の屋久杉が切られた。

その頃を知る山師がいる。本田竜二さんの父・實さんだ。實さんは、数多くの屋久杉と向き合って来た。「巨木を切る技は屋久島イチ」と言われる山師だった。
實さんは2023年に亡くなったが、生前、屋久杉についてこう語っていた。

山師 本田實さん(当時83)
「『縄文杉』より大きい木が何本もまだ残っている。見た目ではそんな感じの木が何本かある」

實さんが言う、その屋久杉の写真が残されていた。幹の直径はゆうに5mを超えている。この木は切らずに、いまも森にあるという。

本田實さん(当時83)
「自分は新しい山に切り込みをする時は、必ず塩米、ある時は焼酎持って行って。人はしなくても自分だけでも山に撒いて、それから作業にかかる。必ず。他の神様には手を合わせないけど、山の神だけは」
私たちは20年近く、實さんら山師の姿を取材してきた。屋久杉は標高500mを超える深い森の中に立っている。山師は自らその木を探し、ヘリコプターで吊るせる大きさに切り分けるのだ。そして一か所に集められ、里に運ばれた。

伐採から50年あまりが経ち、森は再生が進んでいる。しかし、かつてここは国内最大の木材供給地といわれ、500人あまりが暮らす集落が存在した。

その時の映像が残されている。橋を渡ると住宅が立ち並び、理容室や商店があった。学校も作られた。

集落の中を屋久杉を積んだトロッコが走り、屋久杉は人々の暮らしを支えていた。だが伐採は急速に進み、切る木がなくなると山師たちは仕事を失い、1970年、集落は閉鎖された。
1980年代に入ると、残されていた屋久杉も、自然保護への意識の高まりから伐採が中止された。山師は、時代の移り変わりに翻弄されてきたのだ。今は山に残された切株や倒れた屋久杉を切り出し、それらは工芸品に使われている。ぎっしりとつまった年輪は独特の模様を描く。